美術の天才と言えば、真っ先に思い浮かぶダヴィンチ
万能の天才と呼ばれ、美術以外にも、彫刻、建築、工学、音楽などにも驚くべき才能を発揮
特に音楽では即行演奏を得意とし、むしろ当時は画家よりも演奏家として有名だった
録音機の無い時代ですから、現在の我々がその演奏を鑑賞できないのが残念
そんなダヴィンチですが、私生児として差別されたり、学校教育を途中で辞めてラテン語が苦手だったり、いろいろコンプレックスをかかえて悩んでいたようです
それがために、その心理的補償として、人生の途中から自分を神格化することに非常に力を注ぎ、現代の我々がいだく彼のイメージの多くは、その神格化の結果でもあります
彼は意外にも怪獣マニアで、トカゲに羽根をつけて人を驚かしたりするのが大好きだった
上の表紙の絵、ゴジラ映画に出てくるキングギドラ(→)に似ているような気がします
彼が現代に生きていたら、ゴジラ映画に狂喜したことでしょう
多才な人ですから、特撮映画の撮影に取り組んだかも
(^_^;)
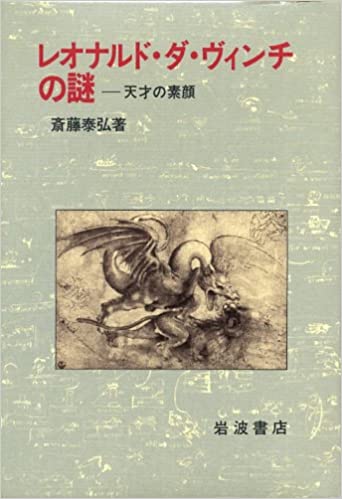





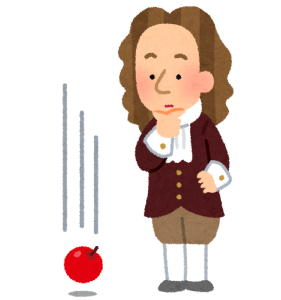

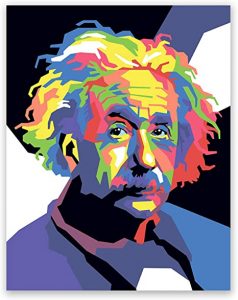
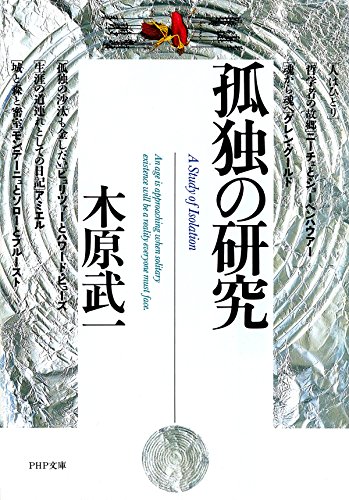

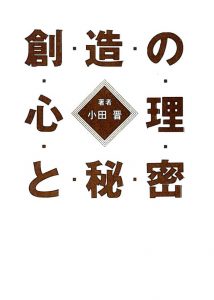


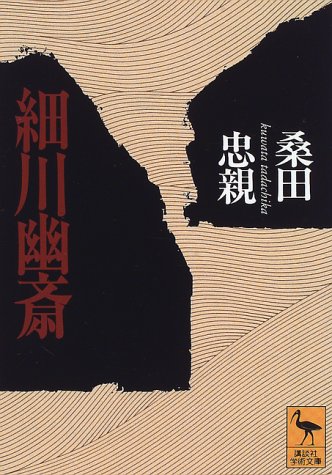
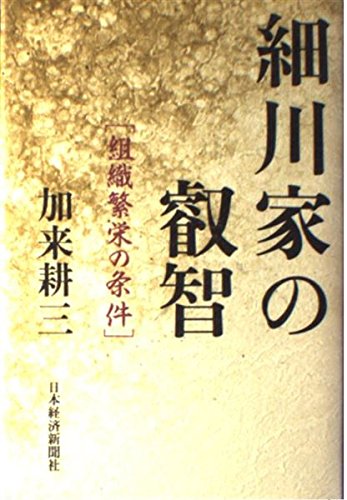

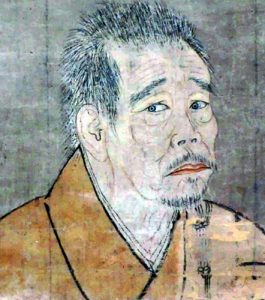


 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト