先日1/6、当ブログで「ベネズエラ電撃作戦」について書きました
この事件(1/3)が起きてから約2週間が経過し、事件の背景や影響についていろいろ情報が出揃って来ましたので、少し書きます
上の動画にあるように、ベネズエラの支配者として王侯貴族のような優雅な生活を送っていた元独裁者のマドゥロ夫妻ですが、今はニューヨークの拘置所に収監中
王侯貴族からいきなり囚人に転落した訳ですから、毎日の生活の快適さは雲泥の差
余りのミジメさに「ベネズエラに帰りたいよぉ」などと訴えて、泣きながら暮らしているそうで、転落した独裁者は哀れなもんです
それでも殺されなかっただけマシで、マドゥロを警護していた親衛隊は、ほぼ全員(40人くらい)が、電撃作戦の当日1/3に死にました
マドゥロ自身も麻薬取引の罪で懲役40年くらいだそうですから、生きて再びシャバの空気を吸うことは難しいでしょう
文明国アメリカの拘置所ですから、北朝鮮や中国の強制収容所みたいな残酷な拷問や虐待はたぶん無いと思いますが、生活環境の落差が非常に大きいですから、さぞかしミジメな気分だろうとは思います
トランプ大統領がわざわざ拘置所まで面会に来て、元独裁者マドゥロを馬鹿にしまくってるという話は少々眉唾ですが、「トランプならやりかねない」という感じもします
今回の電撃作戦は「力による現状変更」であって、ロシアによるウクライナ侵略などと同列に見て、
国際法に違反する!
という非難が、日本の野党やマスコミからも出ています
形式的な法解釈からすれば、確かにその通りかもしれませんが、
国内法とは異なり、国際法には
原則として、警察のような確実な強制力が無い
という点は極めて重要であり、絶対に忘れてはいけません
ぶっちゃけて言えば(私流に意訳すれば)
国際法を破っても、どこからもおとがめが無い
国際法の歴史は、大国による「破りまくり」の歴史
極論すれば、国際法は破られるためにある
国際社会は、サバンナのような弱肉強食の世界
悔しかったら(侵略や虐殺がイヤなら)強くなれ!
または、信頼できる強者に守ってもらえ(日米安保など)
それも無理なら、弱者が集まって同盟を組め(集団防衛)
ということです
これはまさに冷徹なリアリズムの世界であって、国家間の食うか食われるかという残酷な生存競争の世界です
憲法9条をお念仏のように唱えている、薄っぺらい理想主義の世界(頭の中がお花畑の世界)とは正反対
少しでも油断すれば(防衛努力を怠れば)、ウクライナのように領土を侵略されて国民を大量に虐殺されたり、ベネズエラのように国家元首を拉致されたりします
戦争に対する完全な準備を
整えた国民だけが平和を享受できる
という言葉を想い出します
実は北朝鮮に対しても、米軍が独裁者を電撃作戦で拉致(または殺害)しようとする作戦が、過去に何度も計画されていたという説がありますが、実現には至っていません
その理由には、作戦成功見通しの低さと共に、北朝鮮の現体制を維持しておいた方が(泳がせておいた方が)、周辺の大国にとって都合が良いという地政学的な要因もあったと思われます
まさに、冷徹なリアリズムの世界です
((((;゚д゚))))






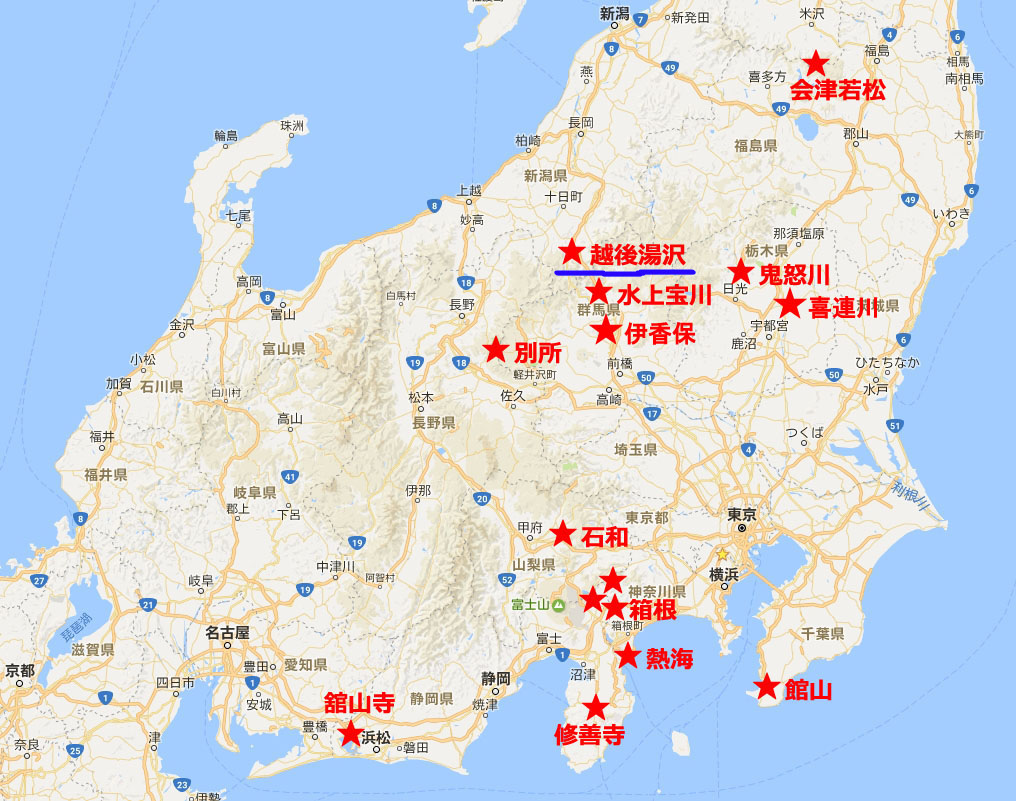







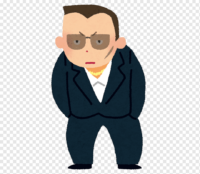
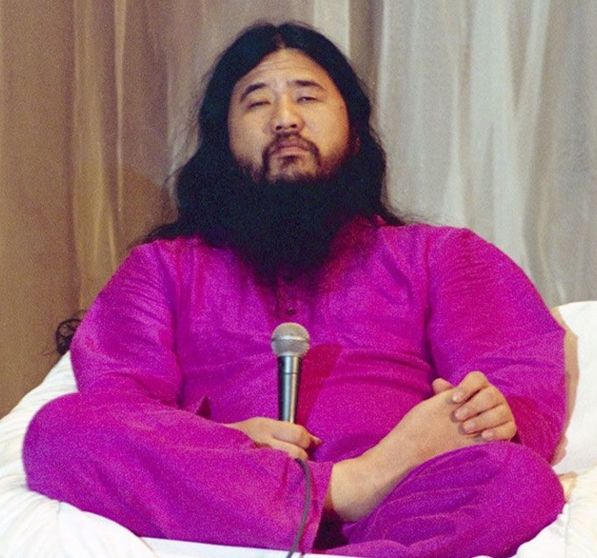




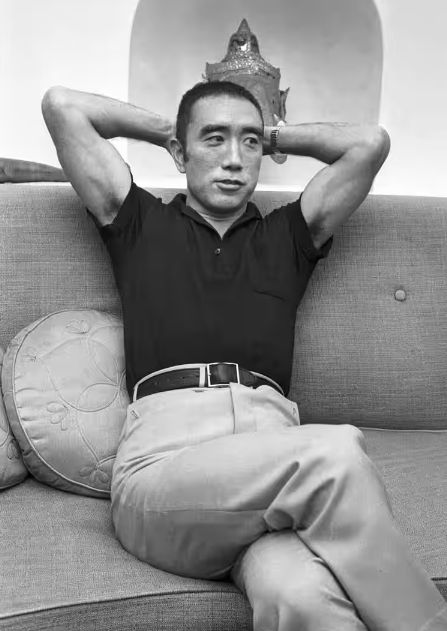

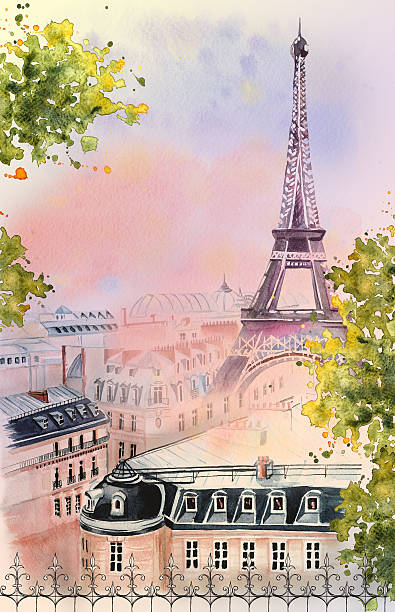

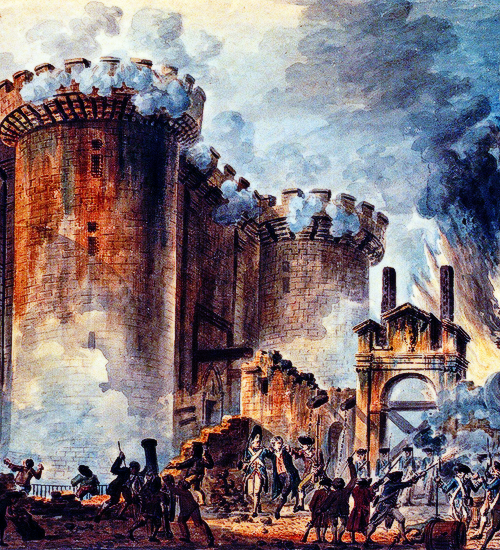
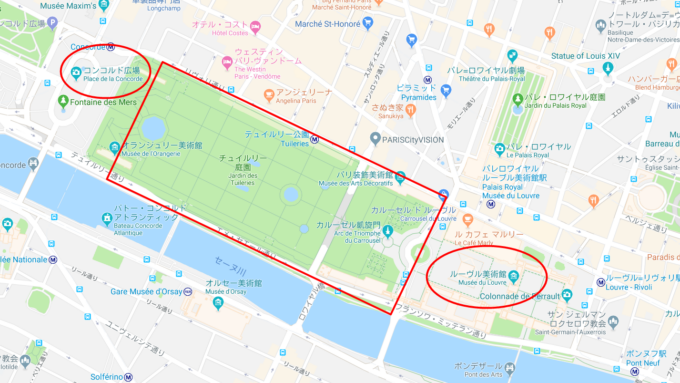
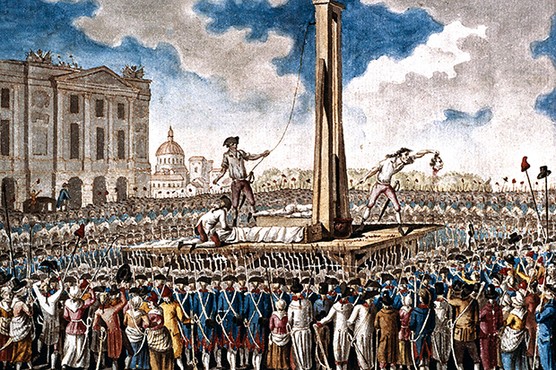
















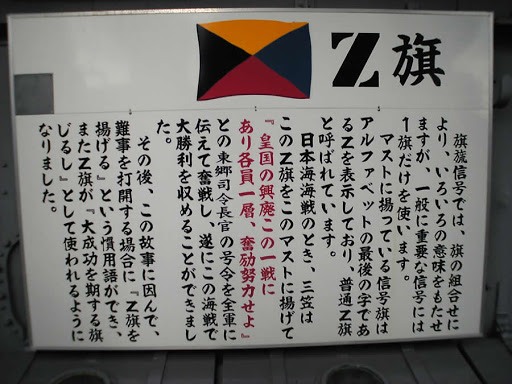

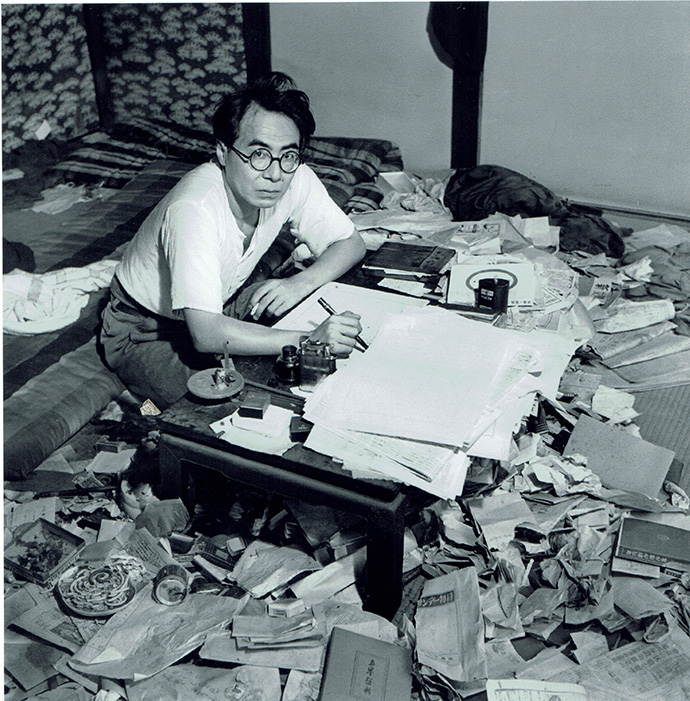



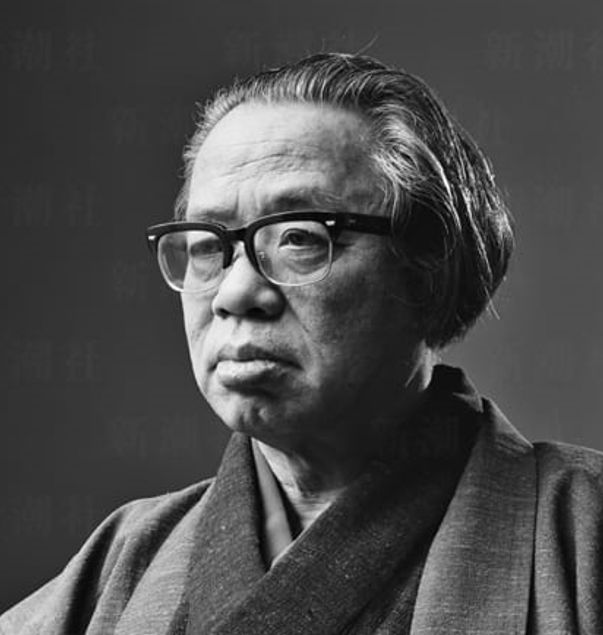






 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト