昨日1/12午後3時ころ、ブタを運んでいたトラックから「積み荷」のブタが逃げたそうです
少しユーモラスで、少し残酷で、少しもの悲しい気分にもなります(この3つは同時に存在することが多い)
我々人類は、動物や植物を利用して生きている
動物や植物の「犠牲の上で」我々の生活(人生)は成り立っている
そのことに過度に反応して、ヴィーガンになったり、罪悪感や感傷的な気分になり過ぎるのもどうかと思うけど、こうゆう生々しい現場を動画で見たりすると、少し感じるところがありますね
自分以外の何か(誰か)の犠牲の上で、自分の生活が成り立っているという現実を直視すると、何やら重苦しい気分になるので、多くの場合、我々は別のことに関心を移して、そんな重苦しい気分から逃れます
これはこれで普通のことで、そうやって我々は毎日を楽しく愉快に生きるし、人生は短いんだから、たぶんそれでいい
「愛の反対語は、憎しみではなく無関心」という言葉もあるけど、常に愛や憎しみで心を満たしていては、ふつうの人の心は疲れてしまう
愛や憎しみ、歓喜、興味、怒り、悲しみ、罪悪感、憂鬱などの気持ちを心の中に持ち続けることは、それなりの「心理的エネルギー」を必要とする
それを長く維持することは難しく、いつかは心理的エネルギーレベルの低い状態(つまり無関心)へと移行していく
常に何かに興味や関心をもって生き生きワクワクしている人、いわゆる「知的好奇心が旺盛な人」というのも時々いるが、それは無関心に移行する前に新しい関心の対象を発見するのが上手な人なのかもしれない
あるいは、心理的エネルギーレベルの高い状態を長く維持出来るという、ある種の先天的な才能を持った人なのかもしれない
何か非常に狭くて特殊なテーマに関心や興味を集中し、それを長い間維持できるという人も時々いて、そこで大きな成果を出したりすると「天才」と呼ばれたりするし、とても幸福な人生と思える
話を元に戻すと、動物や植物だけでなく、人類(人間社会)の中でも、誰かの犠牲(または労苦や努力)のおかげで、我々の生活(人生)は成り立っている
ゴミを処理してくれる人のおかげで、清潔な生活環境が維持できる
ブタや牛、鳥を処理する食肉工場で働く人のおかげで、美味しい肉を食べられる
スーパーやコンビニに陳列してある多くの食品や生活物資は、原材料を調達する人、製造する人、運ぶ人(トラックのドライバーなど)、さらに売る人(スーパーの店員さんとか)たちのおかげで手に入る
これがまさにサプライチェーンという奴なんだけど、普段はその存在をほとんど意識すらしない
ちゃんと対価(お金)を払って利用してるんだから、格別に感謝する必要も無いのかもしれないけど、ふつうは意識すらしない
ときどき、中国がレアメタルの日本への輸出を制限した、などという「事件」が起きて、サプライチェーンの一部が滞ると、そこに関心が向く
もっと考えを広げると、この世(地球上)には相当に悲惨な現場(戦場、虐待、貧困、病苦とか)がいっぱいあるけど、それを直視していると重苦しい気分になるので、我々は別のことに関心を移す(または無関心へ移行する)
一部の人(たぶん少数)は、自分がそんな悲惨な世界とは無縁な、自由で平和で豊かな毎日を過ごせていて良かったなぁ、などと感謝したり喜んだりする
イマジネーション能力の個人差は非常に大きいから、感じるところは人それぞれ
イマジネーション:ふつう「想像力」と訳されますが、何かを頭の中で思い描く能力で、その「何か」とは多くの場合、視覚的で映像的なもの
この世の「悲惨」に対して、ものすごく敏感で、イマジネーション豊かな人がごくまれにいて(例えばブッダとか)、新しい宗教や思想を作ったり、あるいは社会運動を起こしたりします
特に結論めいたことは無いんだけど、そんなもんなんだろうなぁと思います
(^_^;)~♪
▼ジョーン・バエズ、大好き (^_^;)~♪
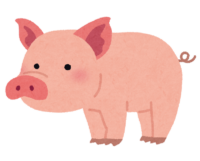


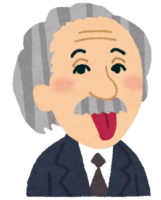


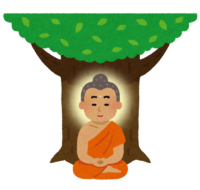


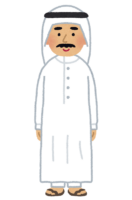




















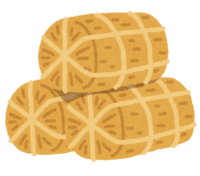
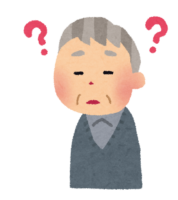



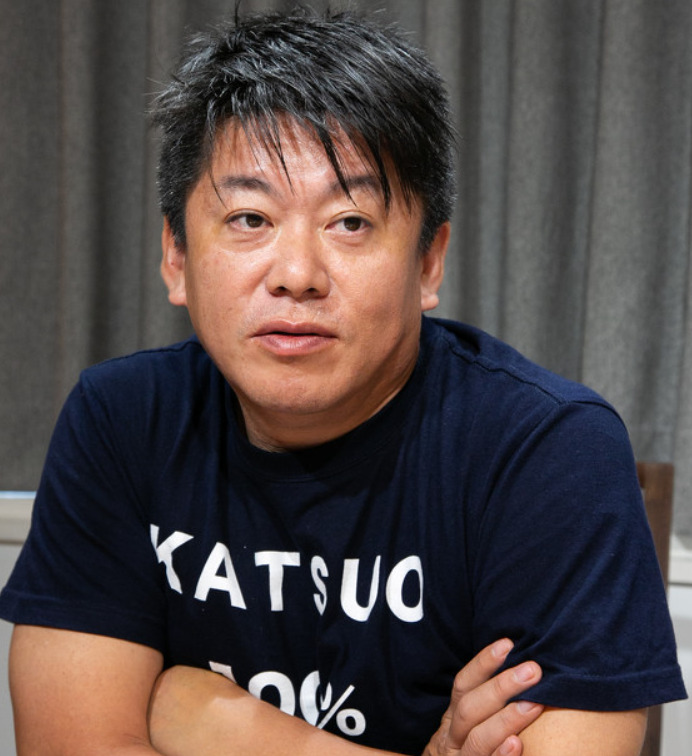










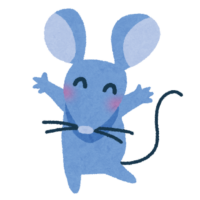







 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト