大学の友人(富士フイルム勤務)に誘われて、アメフトの試合を初めて生で観戦しました
サッカーの時もそうだったけど、建築に興味がある私としては、どちらかと言うと、試合より建物(スタジアム)を観たかったんだよね
先日観たサッカーの国立競技場や味の素スタジアムの新しさに比べて、今日の秩父宮ラグビー場には、歴史の長さを感じました
アメフトのルールは、サッカーとはかなり違っていて、なんだか、距離と時間にやたらとこだわってるスポーツ、という印象でした
試合中に時々、応援団が「ワァー!」とか盛り上がるんですが、何が「ワァー!」なのか、よく分からんかったです
今日の試合は、富士フイルムvs富士通
「富士」つながりですが、ビジネス上はまったく別な会社です
富士通はリーグ最強レベルの強豪で、今日も37対0で圧勝でしたが、応援団の規模は、富士フィルム側が上回ってました
どちらも業界トップの超優良企業で、事業規模で言うと連結売上がどちらも3兆円台と、いい勝負です
富士フィルムチームは、元々は富士ゼロックス(あのコピー機で有名な会社)のチームだったのですが、ゼロックスが日本から撤退したので、チーム名も変えたようです
富士フィルムチームの現在の正式名称は、
あのヘーゲルが「ミネルヴァのフクロウは夕暮れに飛ぶ」と言った、ローマ神話に出てくる女神ミネルヴァなのかな?
すでに写真記録の主体は、銀塩フィルムから半導体メモリーに移行し、富士フィルムもフィルム事業以外に広く事業展開に成功している訳ですが、社名に今でも「フィルム」を残しているのは、何か深いコダワリがあるのかもしれませんね
追伸) いま気付いたんだけど、社名は「富士フィルム」ではなくて「富士フイルム」みたい
「キャノン」じゃなくて「キヤノン」というのと同じだね
ちなみに「富士フイルム」という社名、それまでの「富士写真フイルム」から、2006年に変更されたもの
▼クリックすると拡大します













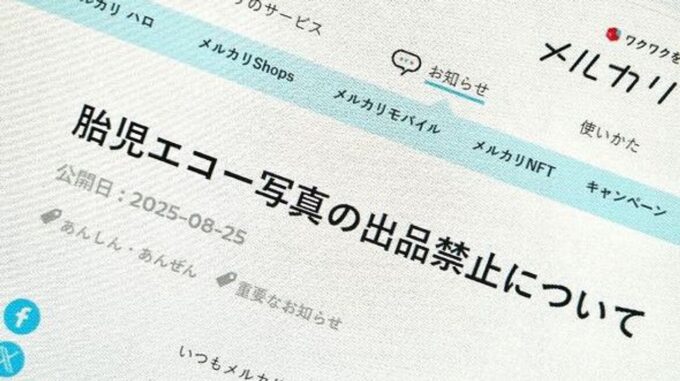




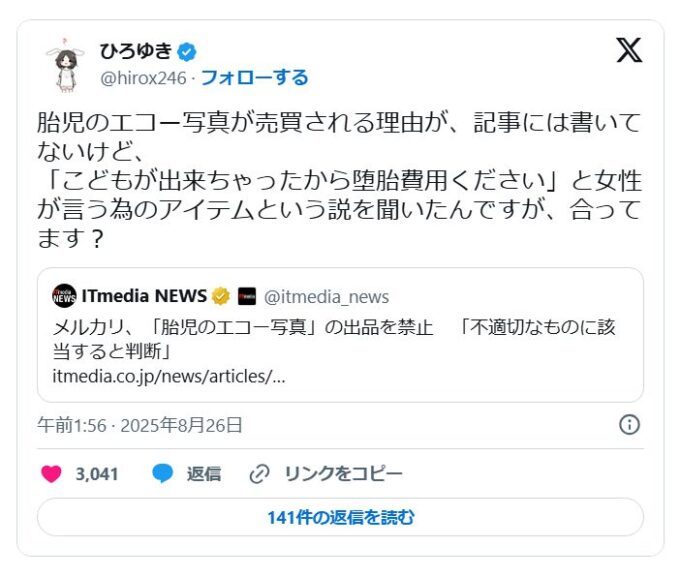










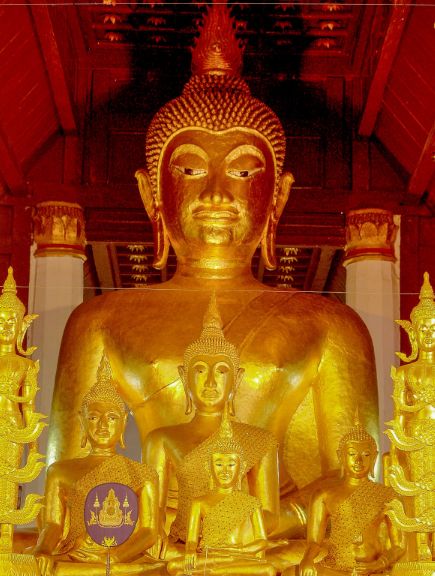






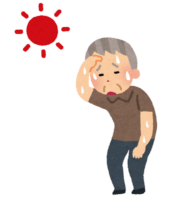






 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト