ギリシャ哲学には非常に多くの哲学者が登場するが、ソクラテスを画期的存在として、その前後と比較している
1)ソクラテス以前 タレスを祖とするイオニア自然哲学
2)ソクラテス 自然探求から自己洞察(汝自身を知れ)へ
3)ソクラテス以後 プラトンとアリストテレス、そしてピタゴラスの影響
この進化を、子供の認識能力の成長にあてはめ、
0)乳児(哲学以前)自分と外部環境が意識の中で混濁した状態、母親の世話による一種の万能感(泣けば何でも解決)
1)幼児(自然哲学)泣いてもどうもならん事柄に出会い、自分と外部環境(世界)が別な存在であることを徐々に認識し、世界への素朴な好奇心が目覚める
2)思春期(ソクラテス)自己洞察が始まり、自意識と悩みが深まる
3)成人(ソクラテス以後)自己洞察と世界観の統合(失敗する人もいる)
というアナロジーは非常に分かりやすい
つまり、ソクラテスは人類の思春期に登場した、極めて特異な哲学者だったという位置づけ
いささか単純化し過ぎではないかとの批判に対しては、この本がもともと4時間の社会人向けセミナーであると言い訳している
(^_^;)
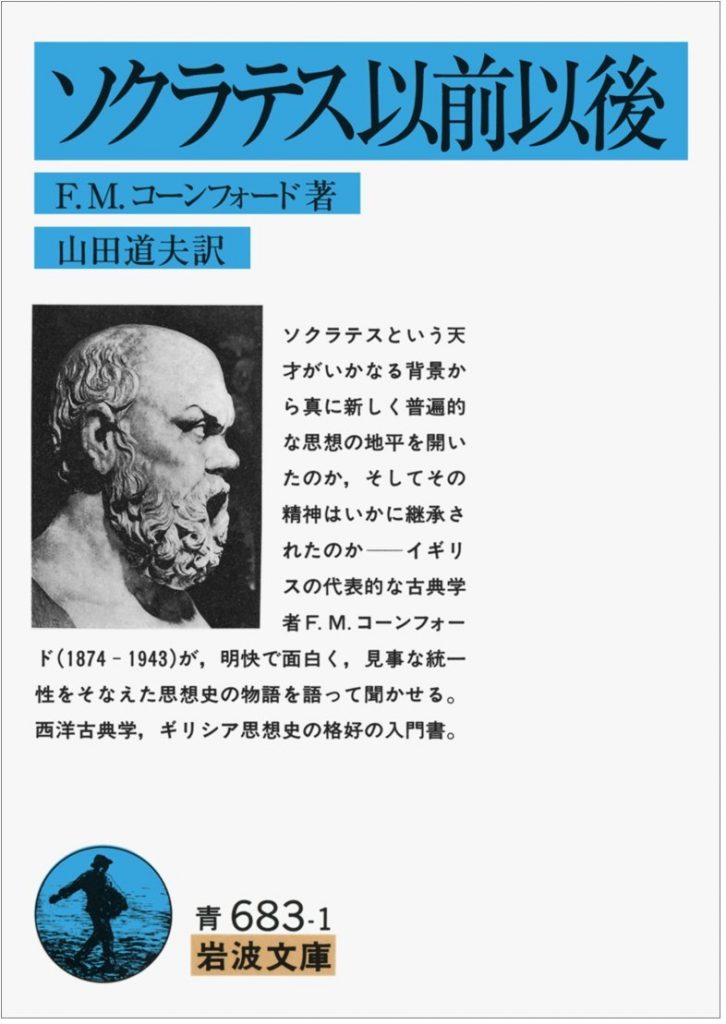
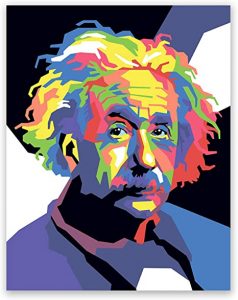
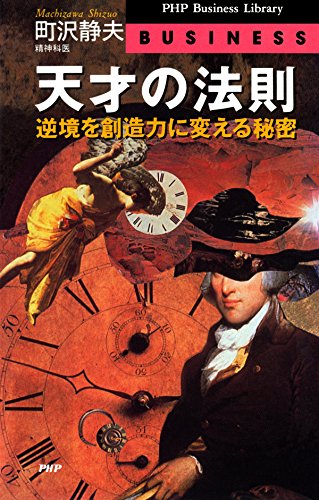
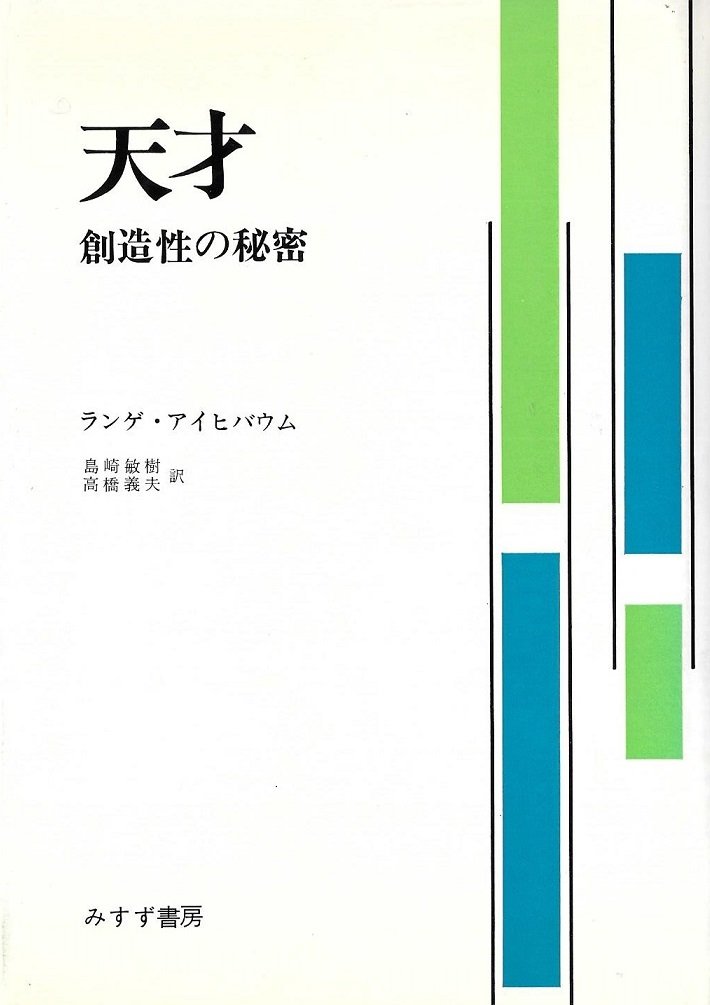




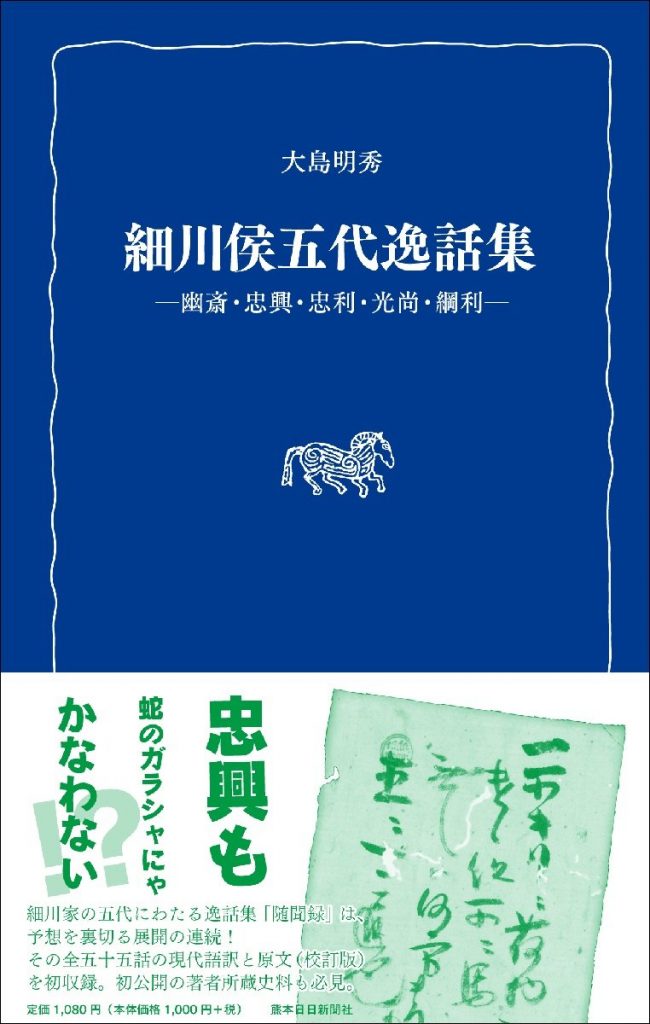

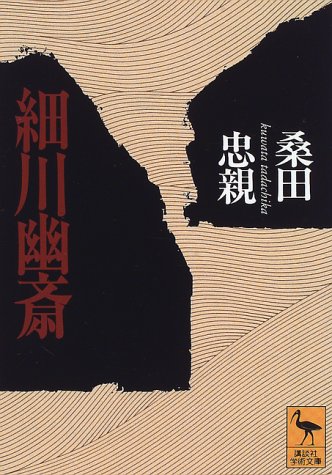
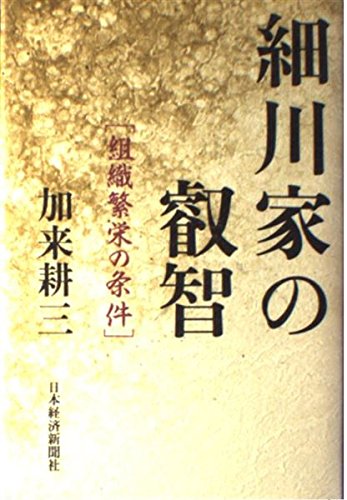

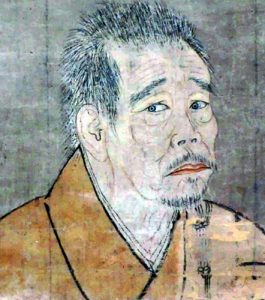


 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト