本物の「男の中の男」は
「つまらない男」の中に
潜んでいるような気がします
(^_^;)
自民党総裁選が9/29投開票され、岸田文雄(64、↑)が自民党総裁に選出された。
「地味」「凡人」「つまらない男」と揶揄される岸田文雄だが、いくら罵倒されても微動だにしないメンタルの強さは〝鉄人級〟と言われる。
元2ちゃんねる管理人の「ひろゆき」(→)から
「地味だという自覚はあるのか?」
とジャブを見舞われた時も
「そうだろうなと思う。無理して、はしゃいだり、
存在感を出すよりも、私の持ち味を理解してもらいたい」
と返し、ひろゆきから
「何で政治家になろうとしちゃったのか。
向いてなくね?」
と挑発されるも
「おっしゃる通り。
改革を目指すにしても、いろんなやり方がある」
と平然としていた。
岸田氏陣営の議員は
「普通だったら、あそこまで言われたら怒るか、
言い返してもおかしくないところ。
だけど岸田さんはひょうひょうと、あの感じで受け流す」
と話す。
広島カープファンを公言する岸田は、中でも〝鉄人〟と言われた故衣笠祥雄(→)を好きな選手に挙げているが、
「岸田のメンタルの強さこそ
〝政界の鉄人〟ですよ」(同議員)。
さらに酒豪でもあり、ロシア外相で酒豪のラブロフとは、朝まで飲み交わしていたほど。
言うまでもなく、ロシア人の「酒豪」というのは、日本の酒豪とは次元が違う。
公家集団といわれる宏池会で、軟弱イメージを持たれがちだが、鋼のハートと肝臓を持ち合わせている。




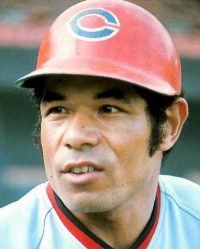



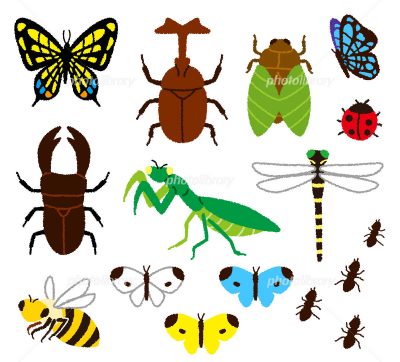


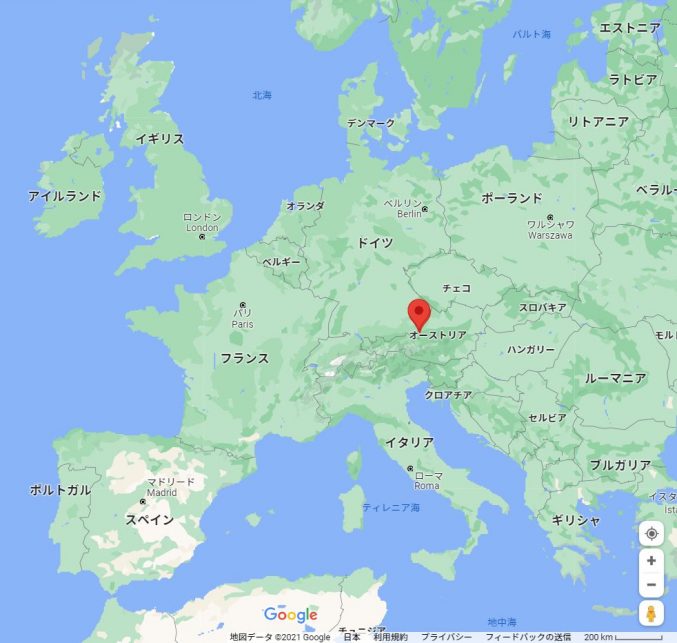

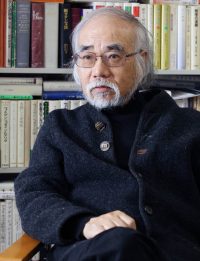




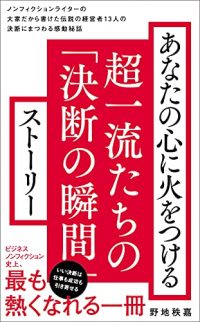

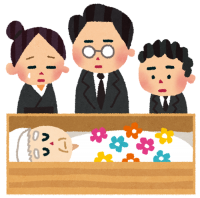



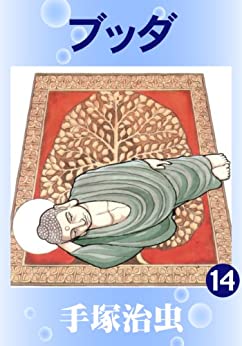





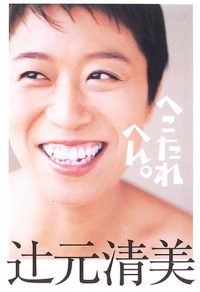


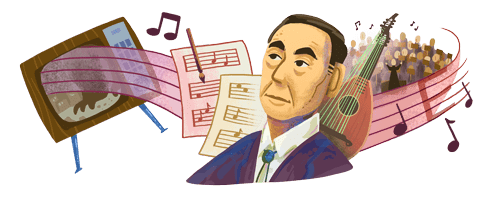


 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト