私は野球にあまり興味が無いし
ほとんど見ることも無いのですが
それでもピッチャーでもある彼の活躍を
ニュースで見て驚いています
(^_^;)
大谷翔平選手の超パワフル15号が話題になっていました。
レンジャース戦で先発出場した大谷翔平選手は、今季トップクラスの速度である117mph(約188.3キロ)という打足で、15号3ラン本塁打を放って米国を驚かせています。
そんな大谷翔平選手のパワーを象徴する本塁打に、海外からは驚きの声が寄せられていました。
海外の反応:
・海外の名無しさん
スイングのスピードがやべぇ。
・海外の名無しさん
スローモーションでもスイングが速いんだけど。
・海外の名無しさん
MVPやサイ・ヤングの可能性のあるピッチャーなんて、生まれてから見たことないよ。
・海外の名無しさん
なんで観客のほうがアナウンサーよりもうるさいの。
・海外の名無しさん
アナウンサーのサヨナラの発音がめっちゃ良くなってるよw
・海外の名無しさん
これでMVPじゃないなんてあり得ないでしょ。
誰にも出来ないことをやって、良いピッチャーであり、すごいバッターだよ。
俺はレンジャーズファンだけどね。
・海外の名無しさん
バットの音を聞いたかよ。
ゴルフクラブみたい。
この子は強すぎだよ!!!
・海外の名無しさん
こんなに速くフィールドから出ていくボールは初めて見たよ。
彼のスイングはマジカルだね。
・海外の名無しさん
1956年からベースボールファンだけど、大谷ほどすごいプレイヤーは初めて見るよ。
世代に一人のプレイヤーだね。
マントル以来の最高のレフトスイングで、ドライスデールとギブソン以来のベストピッチャーだわ。
・海外の名無しさん
いつボールに当たったの?
どこに行った?
あぁ、右の壁を超えてるよ。
・海外の名無しさん
コアに当たってないから、手がしびれてたみたいだね。
どんだけぇ。
・海外の名無しさん
40年ぶりに、また野球を見始めたよ。
最高だね。
・海外の名無しさん
みんながマスクをせずに楽しい時間を過ごしてるのが見られて最高だよ。
・海外の名無しさん
この人はイチローとマツイを合わせたみたい。
しかもピッチャーも出来るという。
MLB史上でも最強のプレイヤーかもしれない。
・海外の名無しさん
数年前は、田中やダルビッシュすら二刀流は無理だって言ってたのに。
エンゼルスのマネージャーもここまでは期待してなかったと思う。
それが今では、生きた漫画キャラになってる。
見てるだけで楽しいよ!
健康を維持して長くプレーしてね。
・海外の名無しさん
大谷のバッティングを見られることを期待して、ジャイアンツ戦のチケットを買ったよ。
美しいスウィングだな。
・海外の名無しさん
エンゼルスがあまり強くないのが残念だよ。
トラウトと大谷をプレーオフで見たいのに。
・海外の名無しさん
右翼ホームランって大谷にはかなり珍しいよ。
・海外の名無しさん
仕事中にエンゼルスが買ってるという通知が入ったから、大谷が何かすごいことをしてるんだろうと思ったけど。
その通りだったね!
彼はマジでモンスターだよ。
・海外の名無しさん
エンゼルスは外野の人たちを保護するネットを張らないの?
こんなんミサイルだよ。
・海外の名無しさん
ゴジラ・マツイ以上の名前って何なの?
・海外の名無しさん
↑超サイヤ人・オオタニ
・海外の名無しさん
今年は自信がめっちゃついてきてるのが分かるね。
ボスみたいにバットを降ろしてるよ。
・海外の名無しさん
↑以前は必死で走ってたのを覚えてるよ。
ホームランじゃないと思ってたのは、アリーナで彼だけだったのにw
・海外の名無しさん
ホームランダービーで彼を見たいよ。
・海外の名無しさん
3月に彼がMVPになるのに賭けたよ。
当たれば100ドルが2500ドルになる。
・海外の名無しさん
二球目でこれをやってたら、118mphにはなってただろうな。
・海外の名無しさん
ブラディのほうがリーグのホームランでは勝ってるけどね。
・海外の名無しさん
↑ブラディはすごいけど、ピッチャーは出来ないし、ホームランも1本差だよ。
どちらも大好きだけどね!
・海外の名無しさん
彼のハイライトはいつ見ても楽しくなるよ。







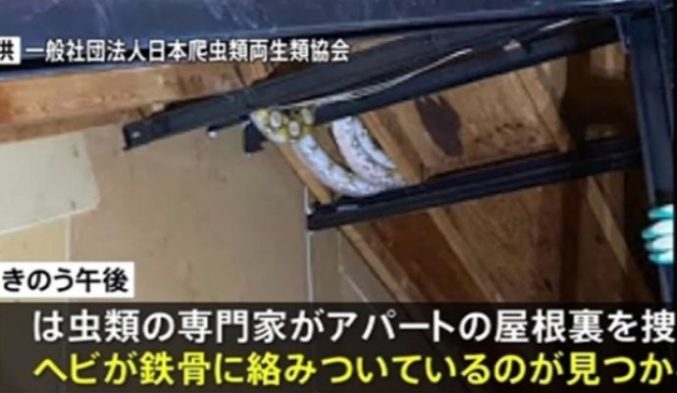







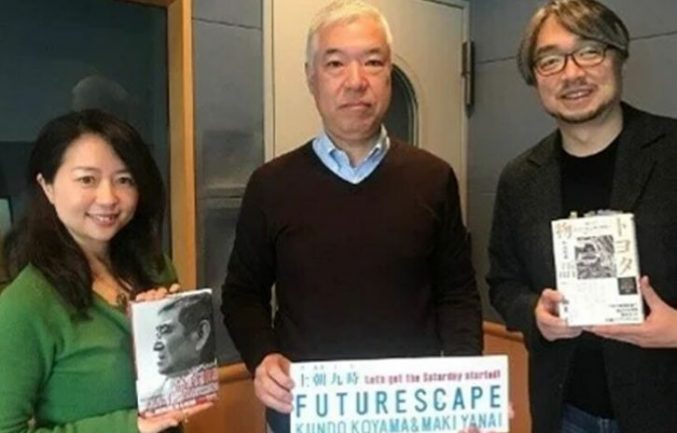








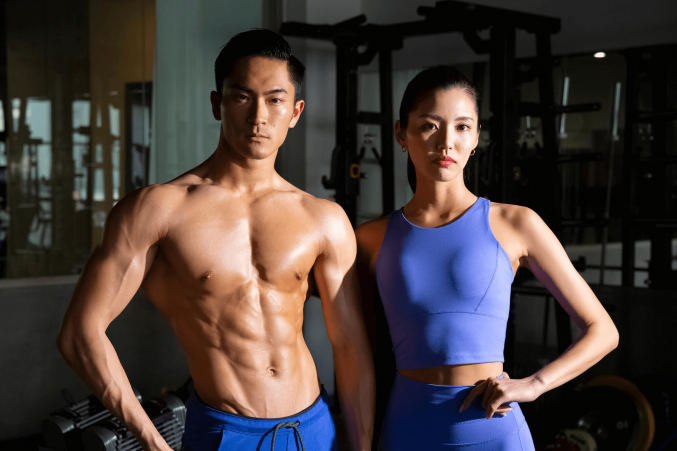







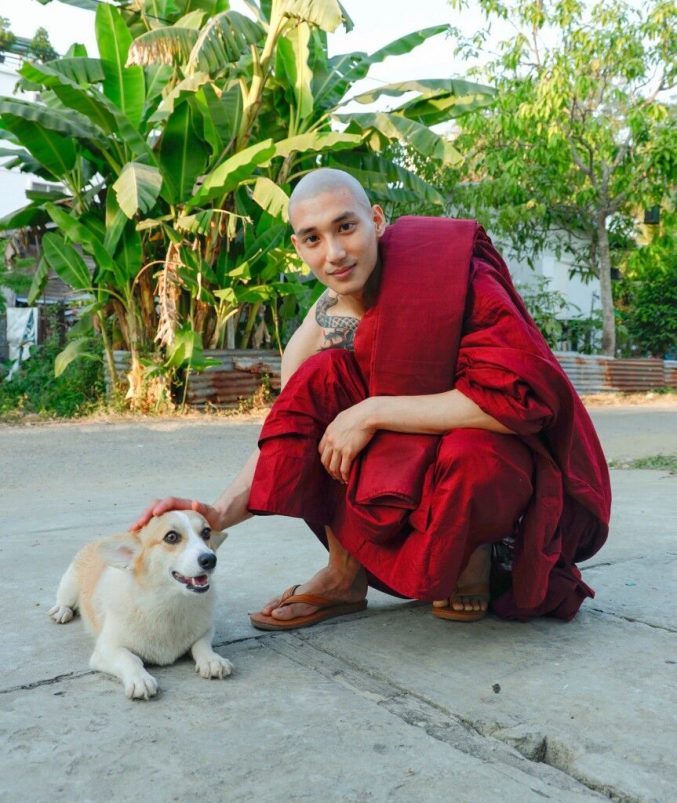


 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト