
久しぶりにスポーツを観て
心の底から感動しました!
(T_T)
競泳の東京五輪代表選考会を兼ねた日本選手権2日目が4日、東京アクアティクスセンターであり、女子100メートルバタフライ決勝では白血病から復帰した池江璃花子(20)=ルネサンス=が57秒77で優勝。
400メートルメドレーリレーの派遣標準記録(57秒92)を突破し、リレーメンバーとしての東京五輪代表入りを決めた。

電光掲示板を確認した池江の目にみるみる涙があふれた。
「今までのつらかったことが、
あの一瞬ですごく思い出された。
ここまで戻ってこられたんだと」
闘病中の写真→
感情を整理するように時間を置いてプールサイドへ上がると、また顔を覆った。
代表を争ったライバルたちが、悔しさを脇に置いて次々と池江を祝福した。
2月末の東京都オープンでのタイムは59秒44。
バタフライは体力の消耗が激しく、池江自身も
「この種目で戦えるようになるのは先のこと」
と苦戦を覚悟していた。
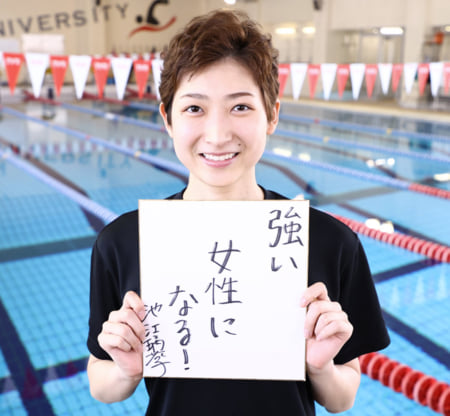
3日の予選、準決勝と泳ぐたびにタイムは縮めた。
それでも五輪切符は難しいのでは、それが大方の見方だった。
予想を覆したのは天才肌の勝負眼だ。
決勝では、準決勝まで苦しんだターンを
「スタートからのドルフィンキックの数を変える」
ことで調整。
後半に向けて体力を温存する策も的中し、残り25メートル付近でトップに立ち、タイムも57秒台まで引き上げた。
「何が起こったのか。気持ちの整理がつかない」
神懸かり的なレースだった。
この2年間の歩みは苦難に満ちていた。
女子自由形とバタフライで次々と日本記録を塗り替え、東京五輪の主役と目された天才スイマーが白血病を公表したのは2019年2月。
長い闘病生活に入った池江にとって、五輪どころか、人生そのものが根底から揺らいだ。
20年3月にプールに戻った時点で体重は約15キロ減。

スタート台から満足に飛び込むことができず、チームメートと練習すると、
「誰にも勝てなかった」
と池江は言う。
東京五輪は1年延期となったが、池江は
「これからが第2の競技人生。目標は2024年パリ五輪」
と明言。
「まず3食をしっかり食べること」(西崎勇コーチ)
から始めた地道な復活への歩みが、一度は諦めた東京五輪を現実にした。
16歳で出場した16年リオデジャネイロ五輪では、100メートルバタフライで5位。
2度目の五輪へ、池江は
「このタイムでは世界と戦えない。さらに高みを目指す」
と貪欲に語る。
新型コロナウイルスに揺れる東京五輪に、大病を乗り越えた20歳が目に見えない力を吹き込みそうだ。
* * * * * * * * * *

池江の所属先であるルネサンスの前社長である吉田正昭氏(64、→)=現同社顧問=も、復活への道のりを支えてきた一人だ。
中学生の頃から成長を見守ってきた吉田さんが、再び五輪の舞台へ立とうとしている池江への思いを語った。
去年の8月の復帰レースの時に、私も辰巳に行ったんです。
璃花子はプールじゃなくて、会場の外にいました。
僕が新木場駅から歩いてきたら、何人かの人影が見えて、その中に璃花子がいたんです。理由を聞くと「中が寒くって…」と。
不安とかドキドキがいっぱいで、1か所に落ち着いてとどまることができないんじゃないか、緊張しているな、と思ったものです。
白血病の一報を聞いたときは、考えられない、信じたくないという思いでした。
世界と戦えるメドが立ってきた時です。そこまでの努力、葛藤も見てきましたが、それが一瞬にして消えました。
言葉になりませんよ。生きてくれっていう思い、それだけです。
元気になればプールにも入ればいいだろうし、と。
競技に戻ってここまで上がってくることは考えられませんでした。
ルネサンスにとっても池江璃花子はシンボルチックな選手で、背負ってくれた部分があると思います。決して強い、勝つというだけではない。存在が誇りです。
入院中には会長や社員、選手までメッセージを集めて、動画にして送りました。
お見舞いに行っても、我々の前では「きつい」とか、弱音は絶対吐きませんでした。
体調が悪くて話せないという日は顔だけ見て帰りました。しっかり治療しよう、病院食もしっかりとるように、と言葉はかけていました。病院食が食べられないでいるときには、おいしいサンドイッチを探しに行ったりもしました。
退院して、去年の3月にプールにつかったときも、まだ泳げる筋力ではなかったと思います。あのときの笑顔は、子供がプールに入ったときの表情。一番うれしいことだったのでしょう。
璃花子との出会いは彼女が中学1年の頃ですが、プールを離れれば完全に現代っ子。ファッションセンスもいいし、音楽も好きですし。
でもやっぱりプールに入ったら、ひとかきで進む距離、パワーの出しどころ…練習を見ていても、モノが違います。
5年間は病気の制約がありますから、まずは体調に気をつけながら、完治を目指してほしい。
練習量がまだ全然少ない中でこれだけの成績なわけですから、どこかで過去を超える時が来ると信じています。
過去の璃花子は、日本でも例を見ないすごい選手でした。
未来の璃花子には、人間としての可能性も含めて、もっとスケールの大きな人になってほしいと願っているんです。
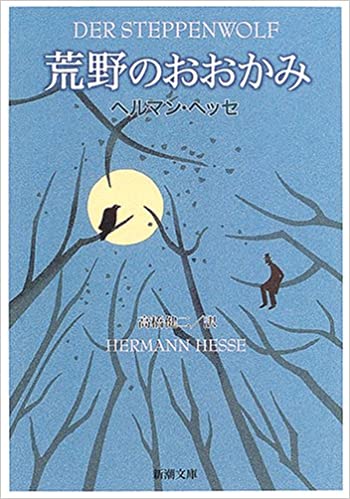

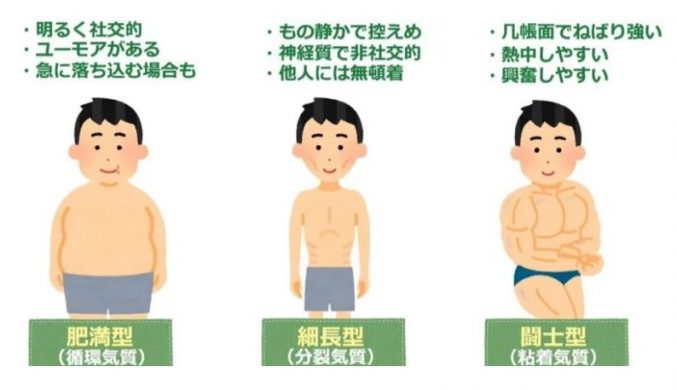



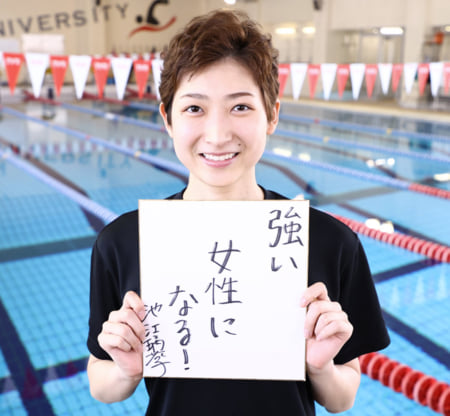





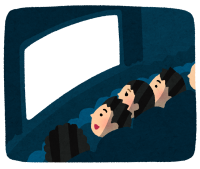
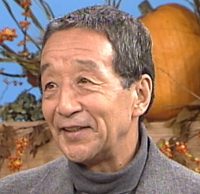


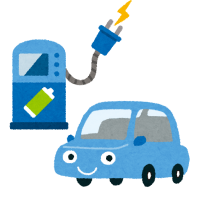





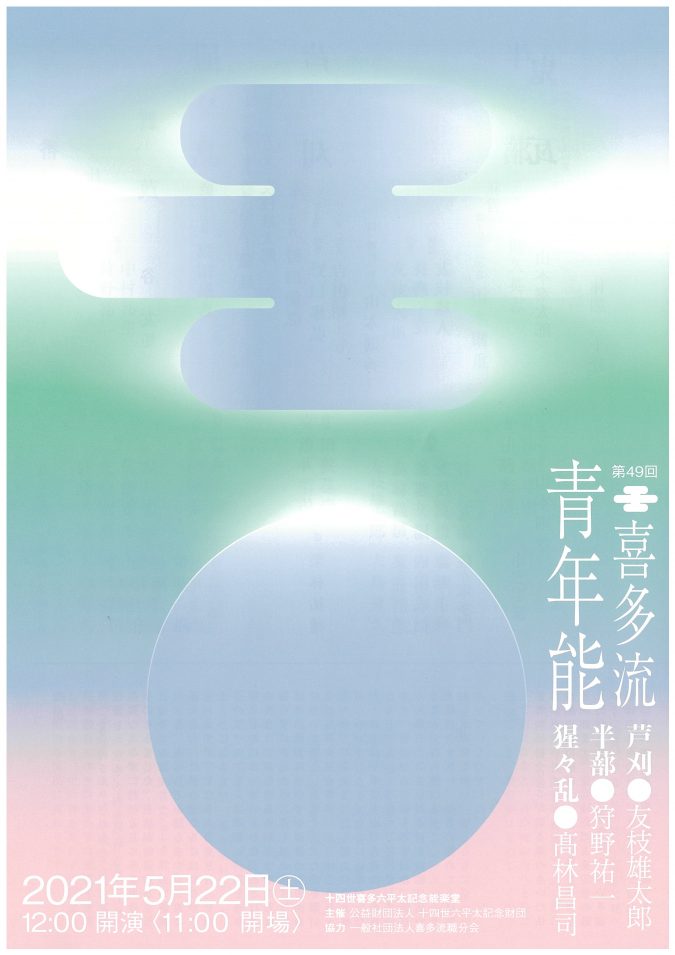


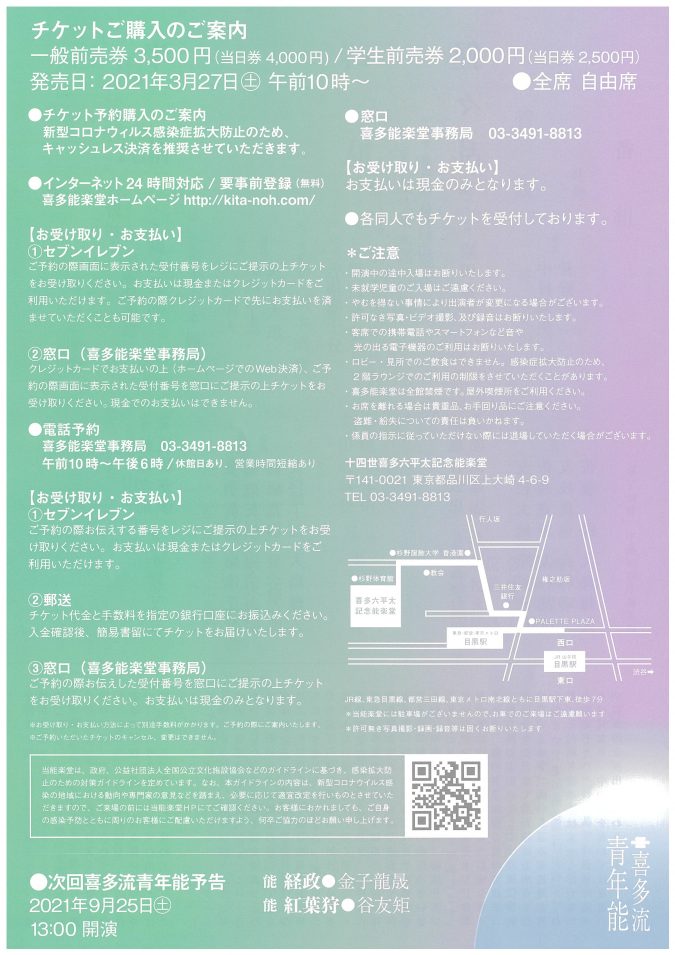





 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト