中年女(製薬会社を経営)との逆玉に乗った若い夫(薬学専門家)が、彼女のすさまじい支配欲にウンザリして若い女と不倫を始める
こんな女房なら誰だって不倫するだろなぁ、という感じで若い夫に感情移入
やがて若い夫が遺産を狙って中年女を毒殺するという、刑事コロンボのような展開だが、場所はロスではなくスペイン
しかもモルグ(遺体安置所)から中年女の遺体が消えるという異常な事件が発生
ミステリーとして非常によく出来ているし、ホラー的な要素もあって、グイグイ引き込まれます
ソニー映画が制作してるせいか、映画の中にやたらとソニー製品が登場するのが笑える
(^_^;)
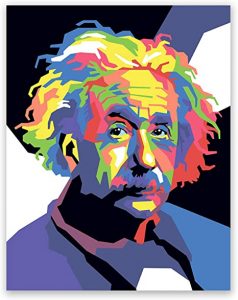
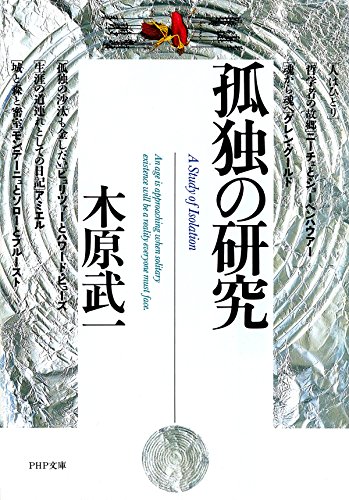
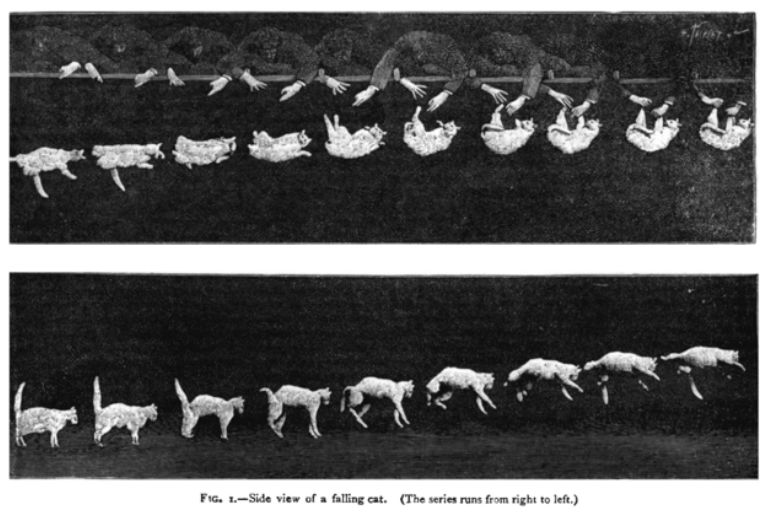

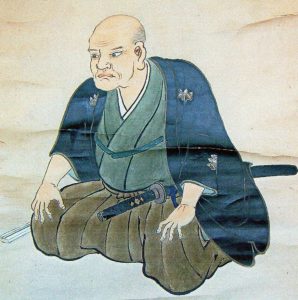

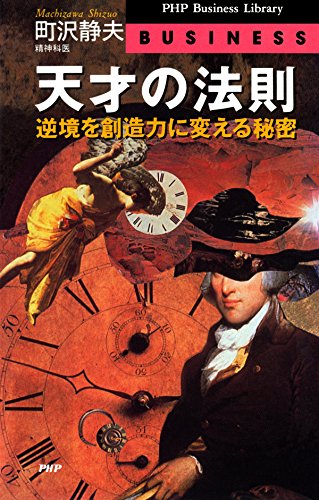
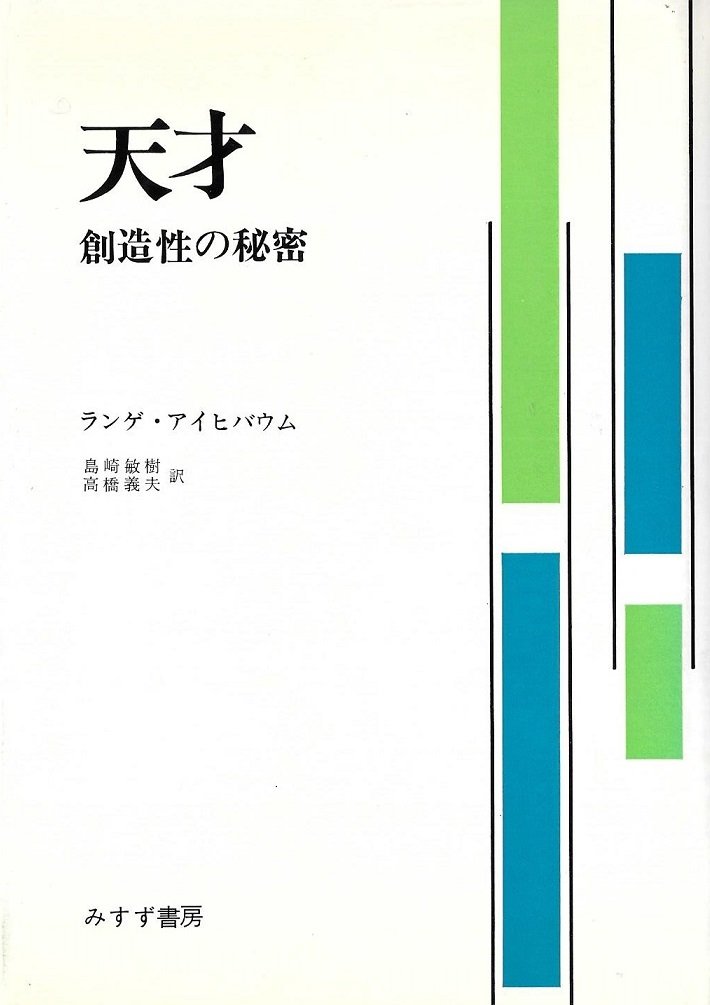
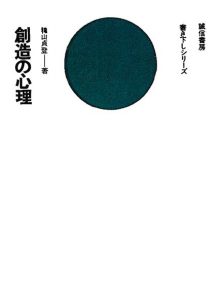
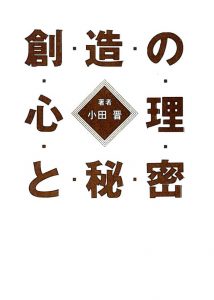




 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト