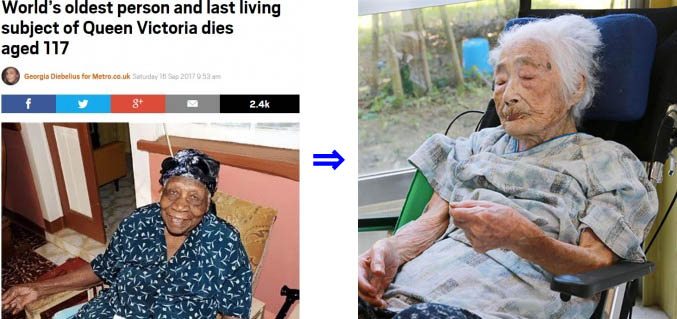
カリブ海のジャマイカからの報道によると、ギネスブックが世界最高齢と認定している同国の女性、バイオレット・ブラウンさんが9月15日、西部モンテゴベイの病院で死去した。
117歳。体調を崩し、数日前から入院中だった。
ブラウンさんの死去により、鹿児島県喜界町の日本人、田島ナビさん(117)が、次の世界最高齢に認定される見通し。
田島ナビさんは、2015年に国内最高齢となった。
ブラウンさんは、イタリア人女性のエマ・モラノさんが今年4月に117歳で死去したことに伴い、世界最高齢となっていた。
ブラウンさんは、かつて長生きの秘訣を聞かれ、地元メディアに「何でも食べるけど、豚肉と鶏肉は口にしない。あとラム酒も飲まないわ」と語っていた。
やはり暖かい所は長生き?
台風が田島ナビさんの上を通過中 (^_^;)
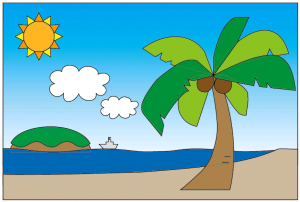




 自民党の
自民党の




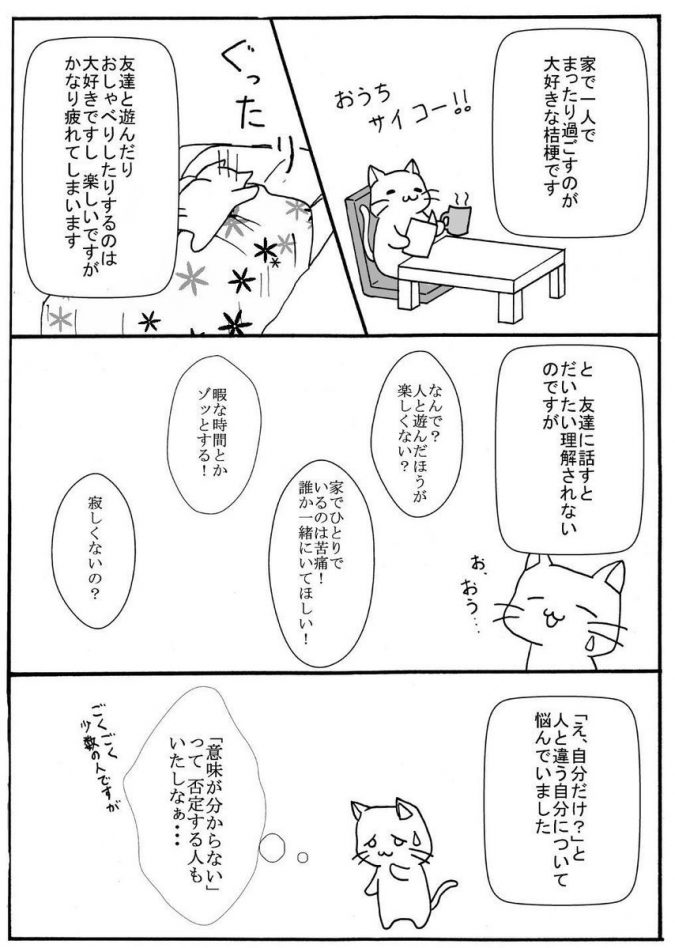




 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト