
12月22日、東京都新宿区の都立新宿高校で「ティーボール教室」が行われた。
新宿高校はこれまでも「Shinjukuベースボールアカデミー」などの社会貢献活動を行ってきたが、今回は日本高野連の「200年構想」の「普及 子ども向けティーボール教室の開催」に準拠した、日本高野連公認のイベントだ。
当初はグラウンドでの開催を予定していたが雨の予報があったために、急遽大体育館で行われた。
田久保裕之監督は「初めてのことだから、何人が集まるか不安」と話したが、約20人の未就学児童が保護者に伴われて参加した。
田久保監督は軽妙な「お話」で、子どもたちをリラックスさせる。
命令口調ではなく「語りかける」口調だ。
まずは、ウォーミングアップとしてダッシュ、ベースランニング。
最初の段階で「ベースを回る」という経験をさせるのは、最後のティーボールゲームを理解させる上で非常に有効だ。
続いて柔らかいボールを使ってボール投げ。
自分でキャッチ、弾ませてキャッチ、そして選手のお兄さんとキャッチボール。
さらに転がるボールを「パクっ」と掴む体験も。
子供たちはボールを使う基本的な動作を身に着けた。
さらにボールを使った「的あてゲーム」「玉入れゲーム」この段階まで来ると、子どもはボールを自分から争って取りに行き、自分から進んで競技に取り組むようになる。
いよいよバッティング。まず選手が、フルスイングでボールをホームランを披露。
そして子どもたちはティーに置かれたボールを打っていく。
バッティングは、未就学児童でも個人差が出やすい。
特に女の子はティーのボールにバットが当たらないことが多い。
そこで田久保監督は段ボール箱の上にティーを置きボールを置いてバットで打たせる「箱ティー」も考案した。バットも少し太めにした。
これで、みんながボールでバットを打つ体験ができるようになった。
ティーボール教室の進行は田久保監督が行ったが、選手たちはイベントの趣旨をよく理解し、子どもがいいプレーをしたら褒めたり、ハイタッチをするなど大いに盛り上げた。
このイベントが、高校球児にとってどんな意義があるのかをよく理解していることが見て取れた。
最後は「どか点ティーボール」。
2面でゲームが行われた。
バットを使うゲームでは、子どもが打ったあとにバットを放り投げるのが危険だ。
今回は、コーンを倒し、その中にバットを入れる動作を子どもたちに教え込んだ。
攻撃側は子どもたち。守備側は子どもたちと選手。
1塁1点、2塁2点、3塁3点、本塁まで帰ってくれば4点が入る。走者は残らないスタイル。
子どもたちは歓声を上げて塁を回った。
通常、ティーボールでは、ゲームの当初は「塁の回り方がわからない」子どもが続出し、それを教えるのに少し時間がかかるが、ウォーミングアップでベースランニングを教えていたので、子どもたちはスムーズに塁を回ることができた。
小さいことのようだが、こうした工夫が、イベントの進行をさらにスムーズにする。
どちらが点が多く入ったかを競い、1時間20分でイベントは終了した。
途中で2回、給水タイムもしっかり取られた。
最後に記念撮影、そして今回は公認イベントで予算があったので、ボール、バット、コーンを使ったティーを子どもたちにプレゼントした。これも重要なポイントだ。
こうした体験は一過性のものに終わりがちだが、ボールやバットを持ち帰ることで、家でもこうした遊びに親しむことができる。
イベント後の保護者のアンケートでは「楽しかった」「子どもがこんなに楽しそうにしているのを久しぶりに見た」「お兄さん、お姉さんが優しかった」「野球ってこんなに楽しかったんだ」などのコメントが寄せられ、評判も上々だった。
こうした取り組みは「200年構想」発表以降、全国で行われているが「誰のための、何のための取り組みなのか」を選手がはっきり理解することがポイントになる。
新宿高校の取り組みは、自分たちが大好きな野球の楽しさを子どもたちにも伝えようという熱意がはっきり見て取れたのが有意義だった。












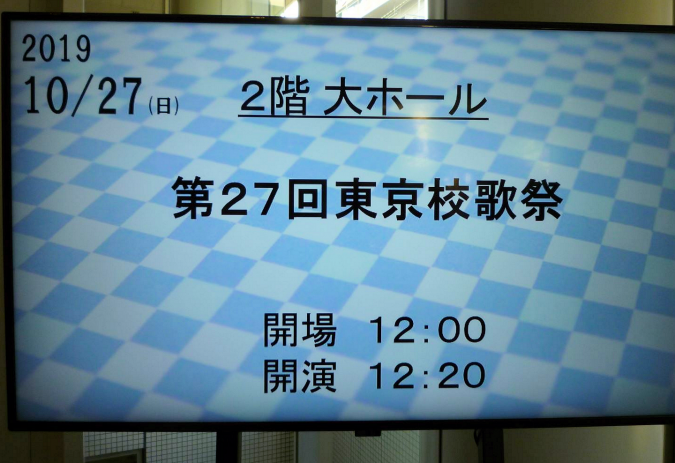



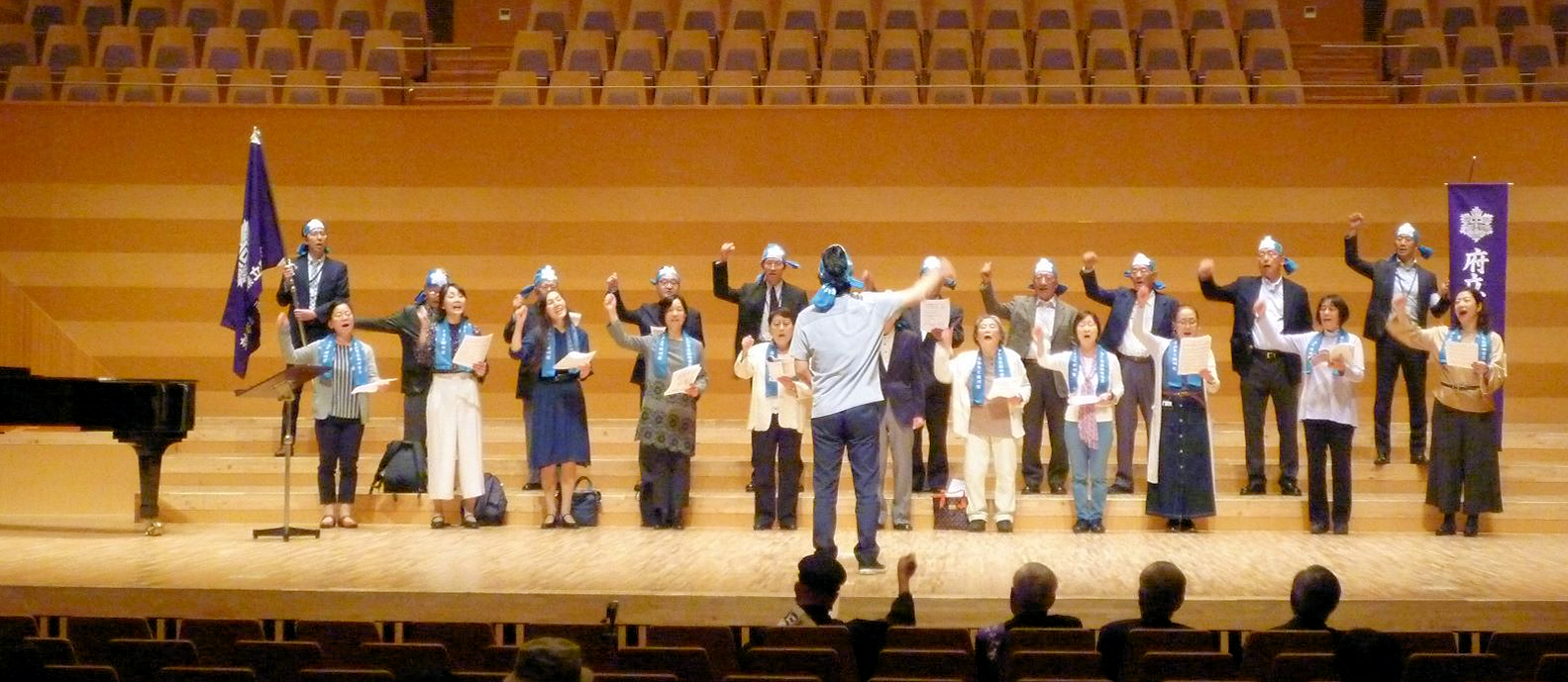






 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト