イギリス人らしい
シニカルなユーモアですね
ぬいぐるみを作ったら
爆発的に売れるかも (^_^;)
中米パナマで発見された目の見えない新種の両生類について、その命名権を獲得したイギリスの企業が「ドナルドトランピ」の名を付けた。
この生物の習性は、気候変動に対する米大統領の姿勢にそっくりだと説明している。
命名したのは持続可能な建築材を手がけるエンバイロビルド(EnviroBuild)。
正式名称は「ダーモフィス・ドナルドトランピ」で、地面に穴を掘って頭をうずめる習性があるという。
同社の共同創業者、エイデン・ベル氏は、「この驚くべき未知の生物と自由世界のあの指導者との類似性を認識した我々は、どうしても命名権を獲得したくなった」と説明する。
ドナルドトランピはアシナシイモリの仲間の両生類で、主に地中に生息している。
およそ6000万年前に手足がなくなり、触手を使って餌を採っている。
「ダーモフィス・ドナルドトランピは両生類なので、特に気候変動の影響を受けやすい。同名の人物の環境政策の直接的な結果として、絶滅の危機にさらされている」
ベル氏はそう解説している。
EnviroBuildは、ポーランドで開かれた第24回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP24)で進展がなかったことにいら立ちを募らせていたという。
熱帯雨林の保護を目的として12月8日に開かれたオークションで、同社はこの生物の命名権を2万5000ドル(約280万円)で落札した。
道路で干からびてるミミズをときどき見ますが
ミミズにとってアスファルトの道路を横断するのは
人間がサハラ砂漠を横断するようなもの
最後にミミズは言います 「み、水~」 (^_^;)

























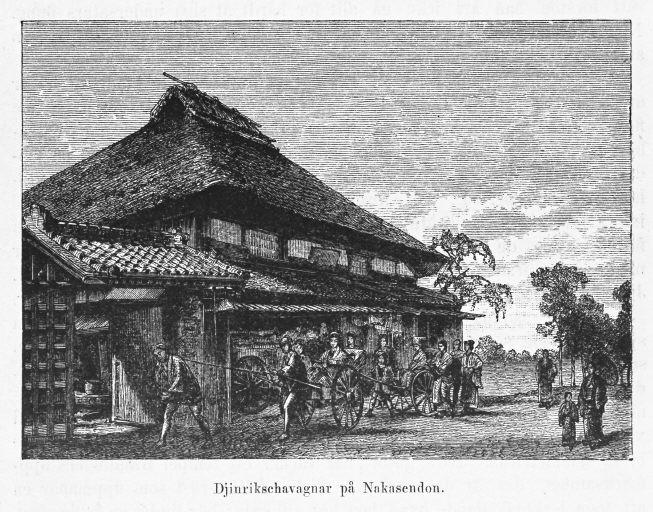










 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト