
とても面白い本だとのウワサは以前から聞いていたが、諸般の事情により(ルネサンスとか、他のことに興味をひかれて)、今日まで読まなかった
そして今日読んでみて、もっと早く読めば良かったと後悔した
本当の偉大な発見とは、まったく新しいものを見つけることではなく、それまで日常的に見慣れていた光景が、まったく別の様相を帯びるようになる、そのような視点の発見であるとよく言われる
ソクラテス、コペルニクス、デカルト、ニーチェ、ニュートン、ダーウィン、フロイト、マルクス、アインシュタイン、みんな新しい画期的な視点を発見した
そして本書の遺伝子に関する生物学も、目からウロコが落ちるように、世界の見え方を一変させる
その世界の中には、自分自身もその重要な一部として含まれるので、本書の題名の通り「そんなバカな!」という叫びが生じる
実際に視点を発見したのは、本書の中に登場する生物学者たちだが、著者・竹内久美子は、それらの発見を非常に分かりやすく、かつ面白く、時には挑戦的に説明して、読者をワクワクドキドキさせる
人工物と生物が根本的に異なるのは、製造の元になる型(モデル)の違いだ
人工物は基本的に、一つの型からすべての製品を製造する
車のボディは、まず金型を作り、それをプレスして量産される
金型のようなハードな型もあれば、設計図のようなソフトな型もある

ところが生物では、製品自体が次の製品を製造する際の金型の役割を果たす
伊勢神宮の式年遷宮は、生物に近い原理で建て替えられている、とも言える
車のボディだって、モデルチェンジは生物に似ている
多くの高等生物では、2種類の製品(♂と♀)の金型を組み合わせて、次の世代の製品(子)を製造する
そこに製品の間の微妙な違い(個性)が生じ、世代が進むにつれて、突然変異と自然淘汰を交えながら、摩訶不思議な変化を生じ、すでに見ている現在の世界が現れる
この摩訶不思議な変化(世代交代)のメカニズムを説明する視点が、遺伝子に関する生物学だ

その一部はすでに常識化されて、浮気男仮説(男が浮気をするのは、その方が多くの子孫を残せるから)のように、浮気男の言い訳などに利用されている
遺伝子に関する生物学のごく一部は、動植物の観察と実験によって科学的に確認されているが、残る多くは単なる仮説だ
ただその仮説群が、浮気男仮説をさらに推し進め、常識をひっくり返すほど画期的で面白いので、ワクワクドキドキしてしまう
「美人の方が自然淘汰で有利なのに、なぜ世の中は美人ばかりにならないのか?」に関する説明には、深く納得してしまった
最近、芸能界を騒がせている不倫スキャンダルも、この説明を一部裏付けてるかも
(^_^;)






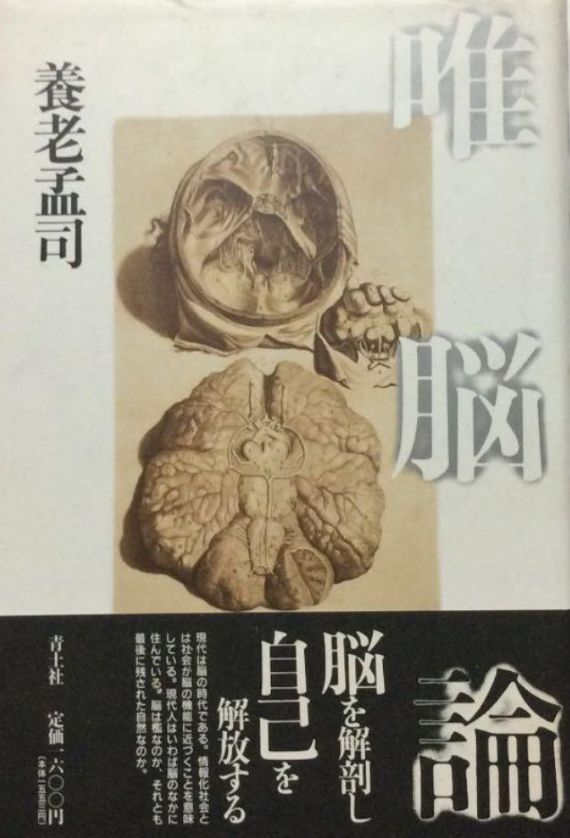


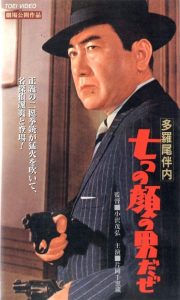


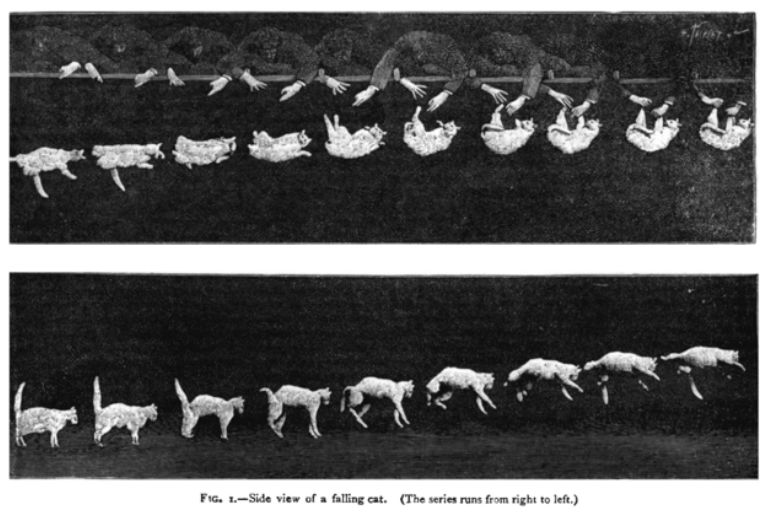

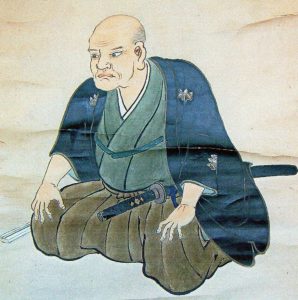

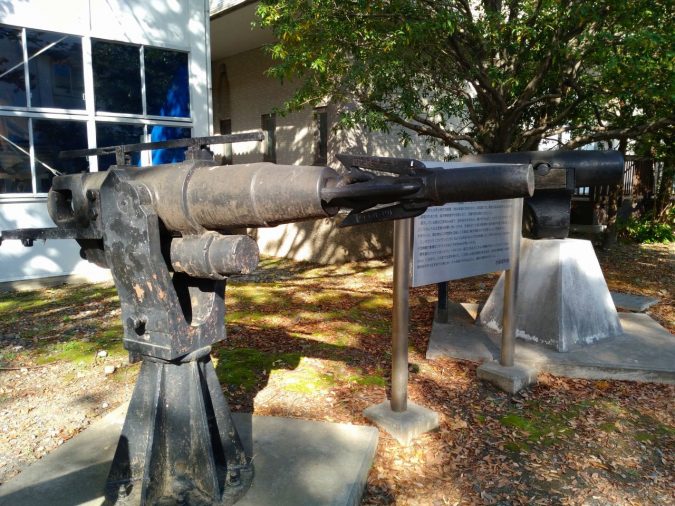


 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト