
サッカーのワールドカップ(W杯)ロシア大会で、日本代表の1次リーグの勝敗を3試合全て的中させた、北海道小平町(おびらちょう)のタコの「ラビオ君」がボイルされて出荷された。
ラビオ君は19日に小平町沖で水揚げされたミズダコ。
漁師の阿部喜三男さん(51)が特産品を広く知ってもらおうと勝敗占いを思いついた。
子供用ビニールプールに、それぞれ日本、対戦国、引き分けを示す3つのかごを設置し、ラビオ君がどのかごに近づくかで占っていた。
初戦のコロンビア戦で「勝ち」、セネガル戦は「引き分け」、ポーランド戦は「負け」と全て的中させたことで、インターネット上では「ラビオ君、半端ないって」などと反響を呼んでいた。
占いには生きのいいタコが適しているため、来月3日未明の決勝トーナメント、ベルギー戦の勝敗を2日に予想する際は、当日水揚げされるタコを「2代目ラビオ君」として起用するという。

いまごろ タコ焼きの具に
なっているかも (T_T)

















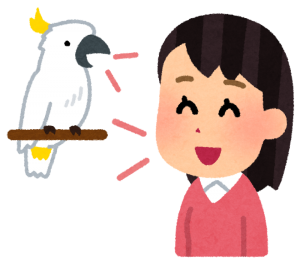


 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト