
中国コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言の発令を機に、大阪市天王寺区の段ボール加工会社「矢野紙器」の段ボール工作セットが、巣ごもり需要を捉えて子育て世代などに好評だ。
同社は

「加工のしやすさが魅力。自分ならではの作品に仕上げ、
ステイホームでの遊びに役立てて」
と語る。
米国の拳銃をモチーフにした工作セットは、男の子がいる家庭に大人気。
引き金や弾になる輪ゴムを引っかける部分には、荷重に耐える力が合板木材と同等の強化段ボールが使われている。
接着剤で張り合わせながら、20~30分ほどで完成させることができるという。
「小さい子には大きめのサイズだが、
軽いから持てますよ」
商品開発担当の島津聖さん(38)は出来上がった段ボール銃を構え、照準を定める(↑)。

温泉街や縁日で親しまれた遊技「スマートボール」を小さくしたセットは最も売れており、購買層の年代も幅広い。
ビー玉をはじき飛ばす部分に、強化段ボールを使用。
玉を受け止めるパーツを思いのままに設定したり、絵を描いたりしながら、二つとない盤面にすることができる。
矢野紙器は強化段ボールを駆使し、ジャングルジムのように子供が乗って遊べる大掛かりな遊具や、高さ数メートルの恐竜のオブジェを作っている。
ショッピングセンターで開かれるイベント用などで貸し出す事業に、15年ほど前から力を入れてきた。
ところが2020年に入り、中国コロナ騒動でイベントが軒並み中止に。
遊具やオブジェの発注が一気になくなる中、自社ホームページ(HP)に限っていた工作セットの販路を昨年4月から広げた。
新たな需要の掘り起こしにつながり、今年1月末までに、予想を大きく超える計約1500点の注文があったという。
「思い描いた形を実現させる楽しさを、ぜひ味わってほしい」
と、島津さんは語る。
工作セットは、、矢野紙器HPと通販サイト「楽天市場」で購入できる。
銃やスマートボールのほかに、よろい、かぶとがある。
いずれも2000円前後と手に取りやすい。

これとはちょっと違いますが、このところ進めていた我が家の寒さ対策の断熱工作で、段ボールは大活躍しています
下の写真(↓)は、引っ越しで使った段ボール箱を広げて貼り合わせて大きな段ボール板を作り、片側(外側)に銀色の断熱シートを貼った、自作の「窓用断熱ボード」です
アルミサッシの窓って金属とガラスだから、熱伝導がすごく良くて、外の寒さが室内にストレートに伝わってしまうんですよね
かといって、二重窓とかにするのは大げさだし、お金もかかる
夜になったら、これを窓サッシの枠にピタっとはめ込むと、外から寒さが伝わるのを、ほぼ完全に防いでくれて、ちょっとしたエコハウスになります

何と言っても、段ボールは軽くて柔らかくて安いです
室内で倒れてもケガしないし、加工も簡単
いらなくなったら、ちぎってゴミ袋に入れて可燃ごみとして出せるので、大型ゴミのような手間がかからない
ネコは段ボールが好き(→)ですが、私はネコも段ボール工作も大好きです
(^_^;)





















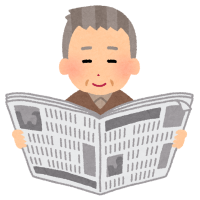


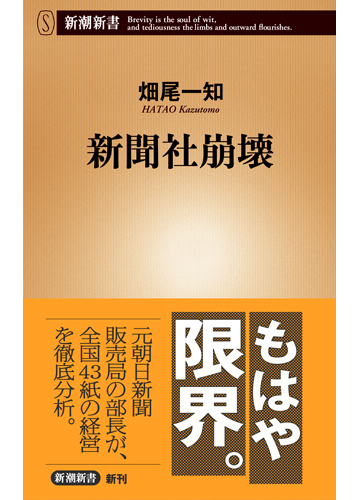









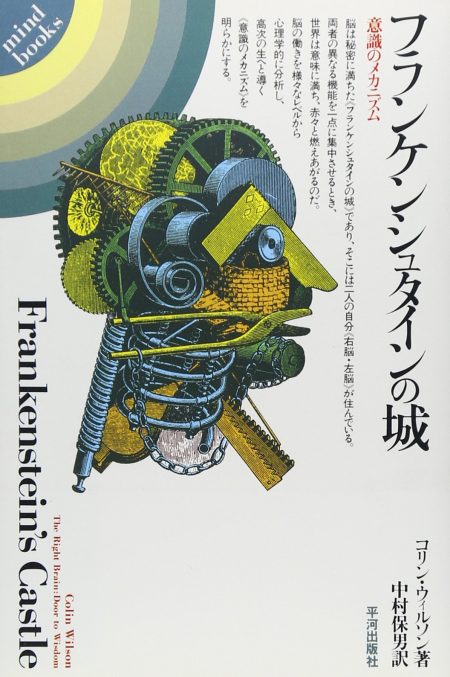

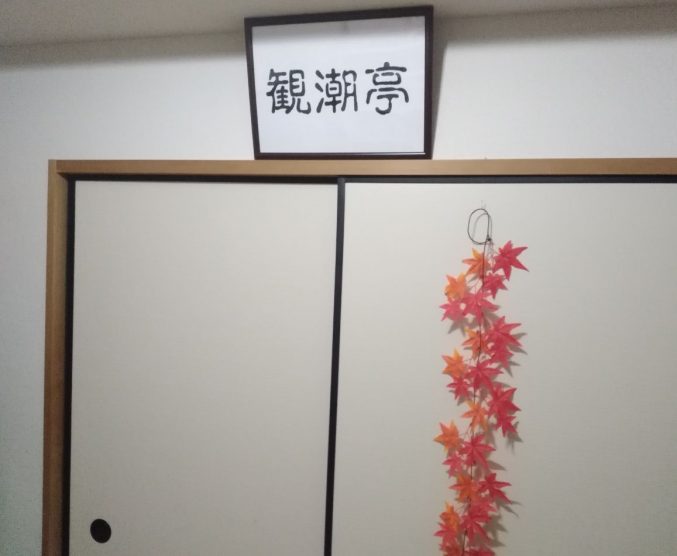
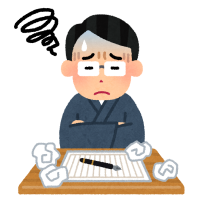





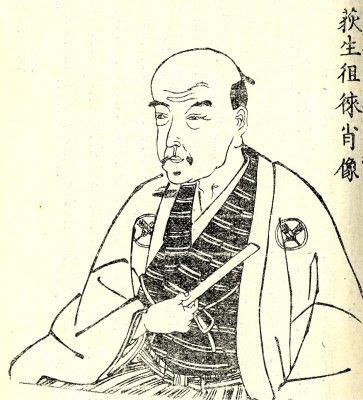


 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト