
▲高輪築堤(たかなわちくてい)
石に白い札のようなものが貼ってあるのは
正確に移築するために、石に番号をふっているのか
鉄道は軍事物資の輸送に重要な役割を果たすのに
明治の初めには、軍が鉄道建設の邪魔をしていた!
なんだか牧歌的な時代精神を感じます
(^_^;)
1872(明治5)年の鉄道創建時に東京湾の浅瀬に築かれ、現在のJR高輪ゲートウェイ駅(東京都港区)西側で見つかった「高輪築堤」が、来春にも佐賀市の佐賀城公園で部分的に復元される。
築堤建設を決めた旧佐賀藩出身の大隈重信(→)の没後100年の記念事業として、佐賀県が乗り出した。
築堤の石約400個を東京から西に900キロ離れた大隈ゆかりの佐賀市に運び、鉄道開業150周年も併せて祝う。
高輪築堤は、新橋~横浜間の鉄道開業に合わせて、現・田町駅付近から品川駅付近まで約2700mにわたり建設された。
佐賀城本丸歴史館(佐賀市)などによると、当時の兵部省(後の陸軍省と海軍省)の反対で付近の陸地に鉄道線路を通すことが出来ず、鉄道建設の責任者だった大隈重信らの判断で、海上建設に踏み切ったという。
当時は品川駅も海岸にあり、海岸から築堤を見て
「海の上を走る陸蒸気」
として観光名所にもなった。

▲東京八ツ山下海岸蒸気車鉄道之図 明治4年(1871)頃
実は明治4年、まだ鉄道は出来ておらず
これらの絵は、海外の資料をもとに想像で描いたらしい
そのせいか、変な形をしている (^_^;)
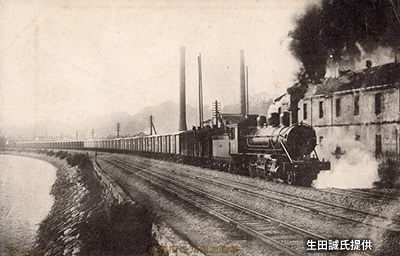
▲現在の田町付近を新橋方面へ走る貨物列車
1906(明治39)年頃、、左下は海
その後築堤は、付近の埋め立てで姿を消したが、JR東日本による品川駅周辺の大規模再開発に伴い、約800mが最近出土した。
このうち、国史跡に指定された120m分は保存されるものの、ほかは記録後に解体される。
そこで
「築堤の石垣から外された石の有効活用を」
と佐賀県が移築に名乗りを上げた。


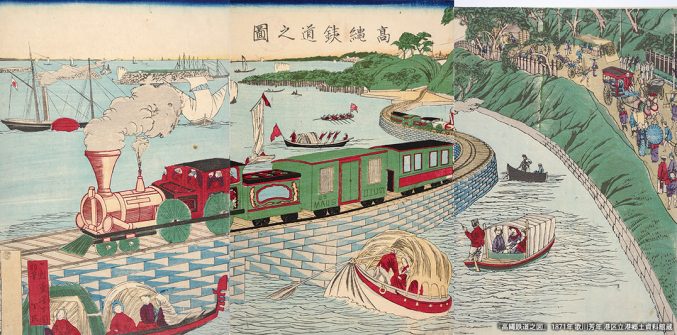






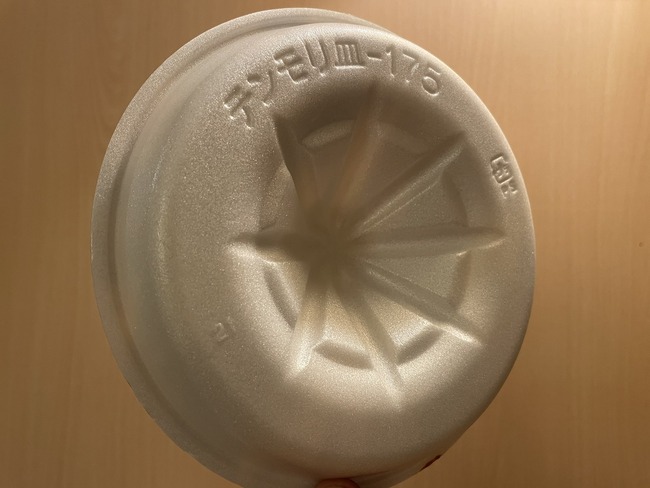



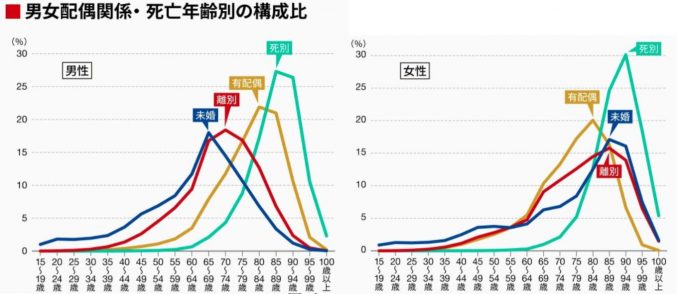





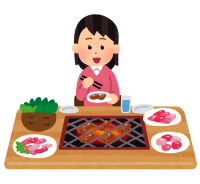
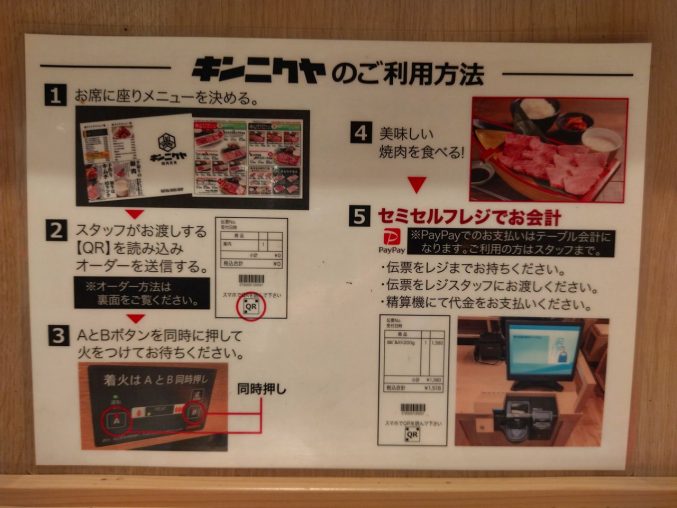
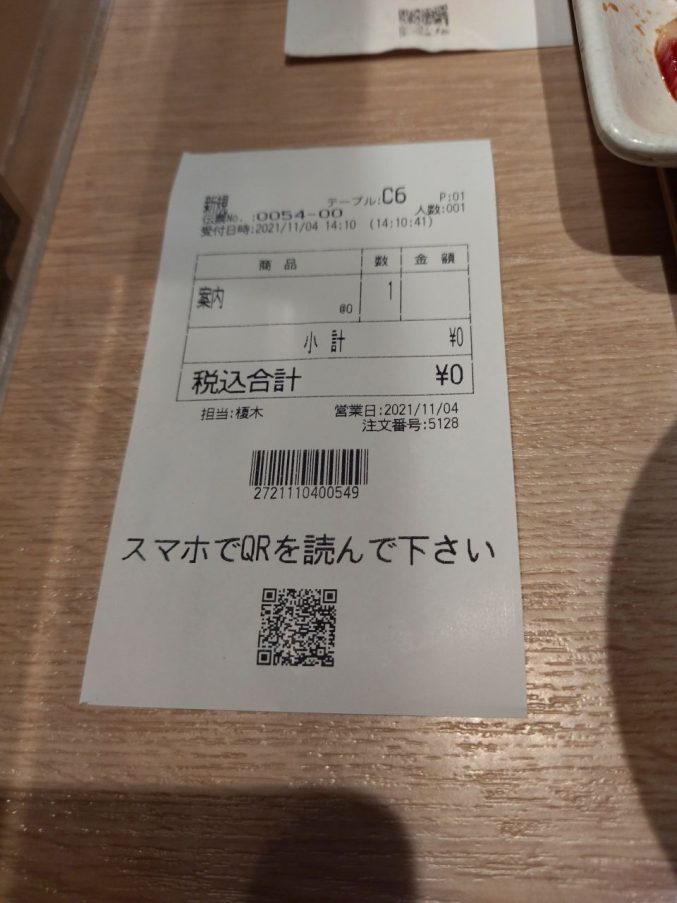

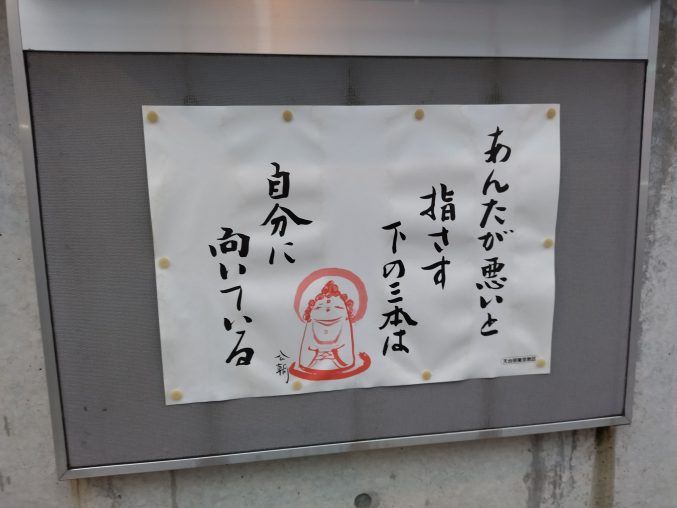

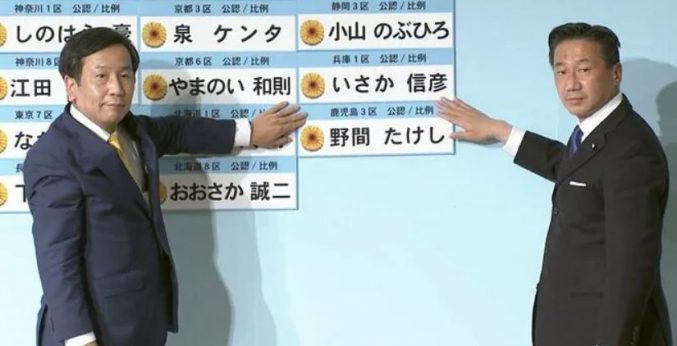


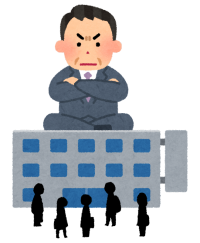



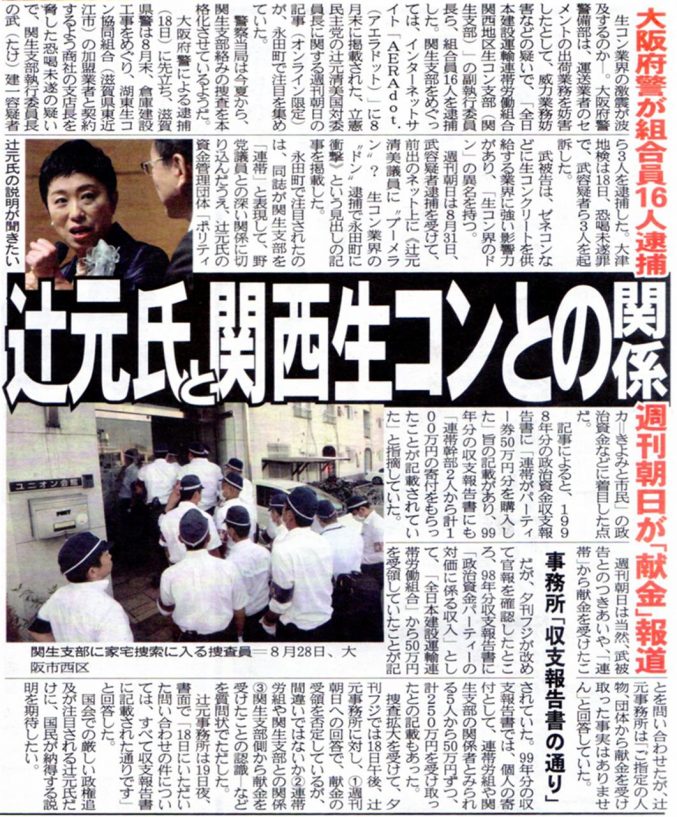
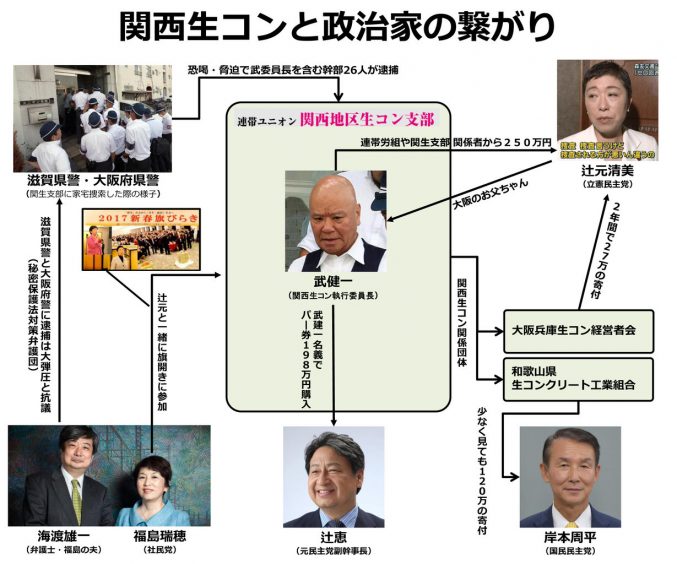


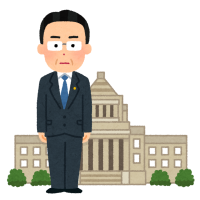


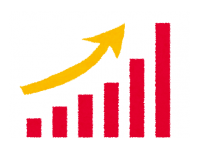


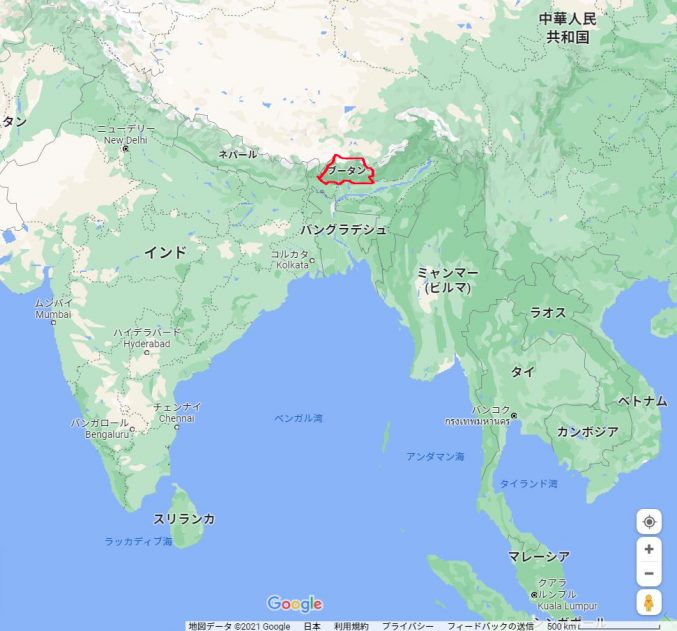


 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト