
硝酸アンモニウムは 簡単には引火しないけど
万一引火したら 非常に恐ろしい!
テロ対策も含めて 日本国内での保管状況を
早急にチェックして欲しい! ((((;゚д゚))))
8/4にレバノンの首都ベイルートで起きた大規模爆発は、同国経済の混乱に拍車をかけそうだ。
3月にデフォルト(債務不履行)を宣言し、新型コロナウイルスが追い打ちとなって激しいインフレで食料不足も懸念されていた。
爆発は経済活動をまひさせ、市民生活をさらに追い込む恐れがある。
爆発は4日午後6時ごろ、ベイルート中心部に隣接する港で起きた。
レバノンのメディアによると少なくとも135人が死亡し、数千人が負傷した。
最大30万人が家を失い、都市の半分に及んだ被害の総額は推定約3000億円超に上ると、知事が5日明らかにした。
マルワン・アブド(Marwan Aboud)知事は
「現在家を失った人は25万~30万人いると思う」
と述べ、爆発の被害総額は30億~50億米ドル(約3000億~5000億円)と推定されると語った。
東日本大震災の、建築物の全壊・半壊は40万戸、避難者は約47万人でしたので、今回の爆発の被害が、とんでもない規模だったことが分かります ((((;゚д゚))))
また、エンジニアや技術班らによる被害状況の正式調査はまだ行われていないが、港湾地区で発生したこの爆発の被害はベイルートの半分に及んだとみられると述べた。
犠牲者の数は膨らむ可能性がある。
アウン大統領は5日に緊急閣議を開き、2週間の国家非常事態宣言を出す考えを示している。
アウン氏は4日に、肥料や爆弾の原料として使われる硝酸アンモニウム2750トンが当局に押収された後、6年間にわたって安全対策が不十分なまま保管されていたと、述べた。
トランプ米大統領は「攻撃」の可能性に言及した。
被害は首都中心部の広い範囲に及ぶ。
ブラジル紙によると、現場から数キロメートル離れたカルロス・ゴーンの自宅も損傷した。
レバノン経済は隣国シリア内戦や原油安による湾岸経済の失速で低迷し、3月には償還期限を迎えた国債のデフォルトを宣言した。
新型コロナの感染拡大もあり、通貨レバノンポンドの実勢レートは対ドルで昨秋の5分の1の水準になった。
現金不足の銀行では預金の引き出しが制限され、激しいインフレが生じている。
懸念は食料不足にまで及び、失業率は3割を超えるとみられる。
レバノンは食料を輸入に頼っており、爆発した港が玄関口だった。
国境を接するのは内戦下のシリアと、敵対関係にあるイスラエルで陸上輸送は困難だ。
ただ、イスラエルは爆発を受け、支援の意思を示している。
ディアブ首相は経済危機を脱しようと、国際通貨基金(IMF)や旧宗主国のフランスなどに支援を求めていたが、条件となる経済改革に抵抗し、協議は難航していた。
3日には政府の無策を批判してヒッティ外務・在外居住者相が辞任を表明するなど、政治的な混乱も広がっていた。
レバノン経済の危機は、18の宗派が権力を分け合う硬直的な政治や腐敗が招いた側面も大きい。
2019年秋には大規模な反政府デモが起き、ハリリ前政権が退陣に追い込まれた。
7日には05年に起きた前首相の父ハリリ元首相の暗殺事件の判決公判が予定されており、対立は激化する恐れもある。


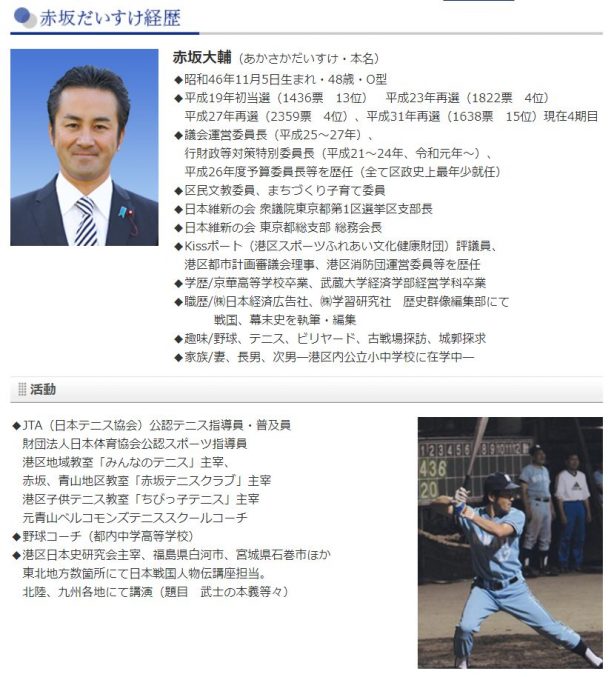
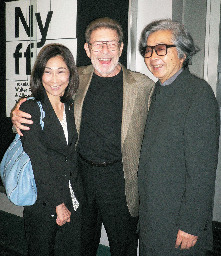






 ▲国際逃亡犯罪者カルロス・ゴーンの豪邸
▲国際逃亡犯罪者カルロス・ゴーンの豪邸





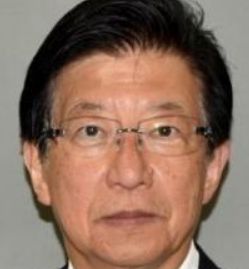


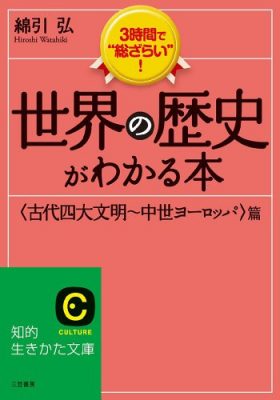
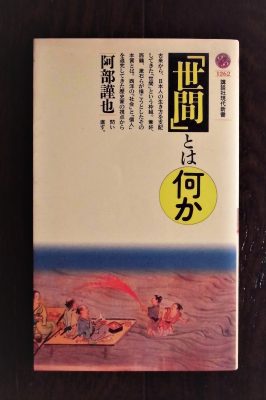


 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト