
品川駅では、リニアの建設(始発駅になる)の他に
京急線の水平化、駅ビルの建て替えなど
大改造計画が進んでいます
(^_^;)
JR東日本は9/14、品川駅の京浜東北線(大宮方面)と山手線(外回り、渋谷・新宿方面)を、12/5から同一ホームで乗り換えられるようにすることを発表した。
現在、京浜東北線(大宮方面)を4番線、山手線外回りを2番線で運用しており、階段、コンコースを経由した乗換が必要。
今回、3番線・4番線ホームを9mから13mに拡幅し、現在設置している囲いを撤去。
現在の2番線の線路を新たに3番線として運用し、新3番線を利用する山手線外回りと、4番線を利用する京浜東北線(大宮方面)を3番線・4番線ホーム上の水平移動で乗換できるようになる。
運用の変更は12/5始発電車から。
悪天候などにより実施できない場合は12月12日からとなる。
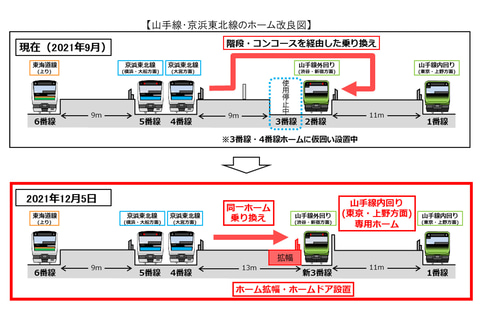
▲今までの山手線ホームは、激混みだったのですが
内回りだけになるので、ゆったりしそうです (^_^;)
▲朝の品川駅
▲クリックすると拡大します
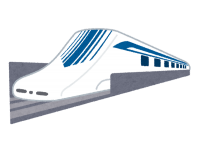


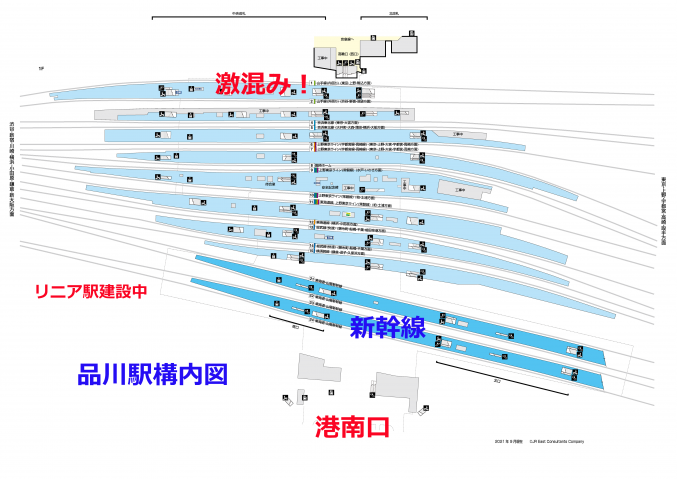













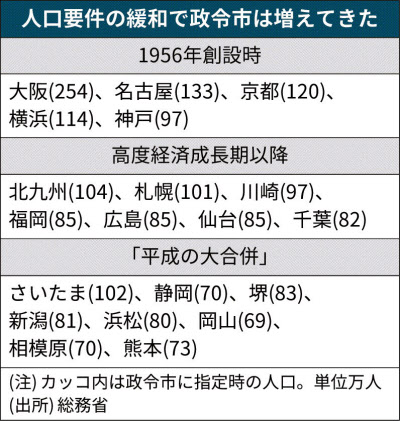


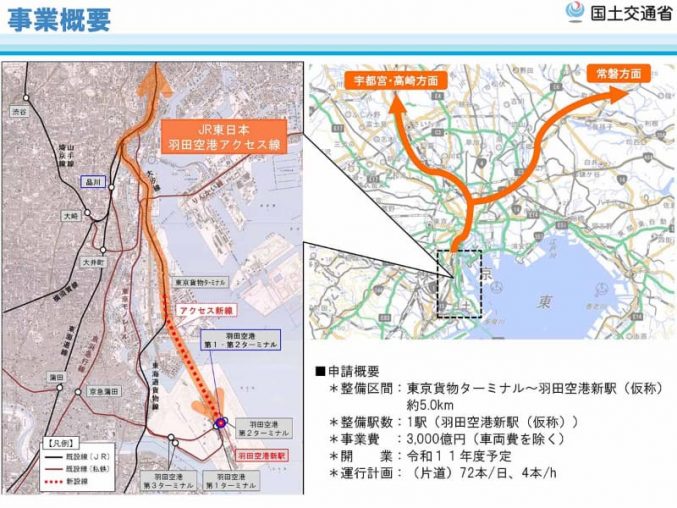

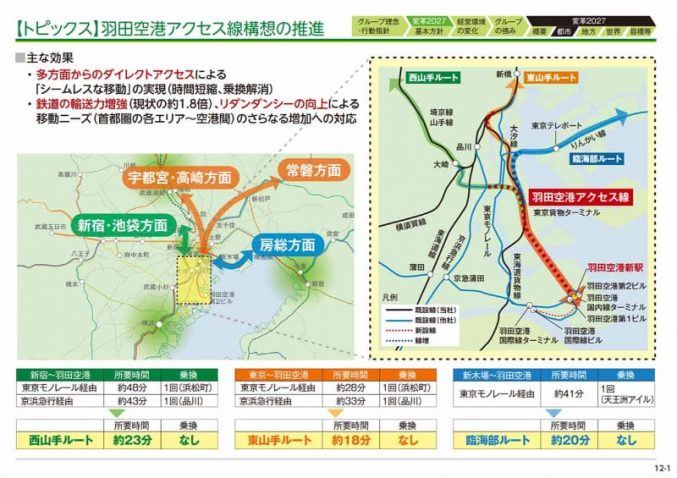





 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト