VIDEO
私はこの映画を過去に十数回は見ているし
世界の映画史上に輝く超名作だと思うので
人類が後世に残すべき偉大な芸術作品
大切に扱ってもらいたいです (^_^;)
米国をはじめとする各国で人種差別と警察の暴力に抗議するデモが拡大し、放送業界が配信内容の見直しを進める中、動画配信サービスHBOマックスは9日、
映画『風と共に去りぬ(Gone with the Wind)』
をストリーミング配信のコンテンツから削除した。
南北戦争を舞台にした1939年公開の同作はアカデミー賞9部門を受賞し、インフレを考慮した興行収益で歴代トップに君臨する歴史大作だが、奴隷が不満を言わず、また奴隷所有者が英雄のように描かれているという部分は批判の的にもなっている。
HBOマックスはコメントで、
「『風と共に去りぬ』には残念なことに、
現在の米国社会でも当たり前となっている
民族・人種差別的な表現がみられる」
「このような人種差別的な表現は
当時も間違っていたし、現在でも間違っている。
これらの表現について説明も非難もせず、
作品を配信し続けることは無責任だと考えた」
と説明した。
アフリカ系米国人のジョージ・フロイド(George Floyd)さんが警察の拘束下で死亡した5月25日以降、反人種差別デモは全米に拡大している。
また、市民の間には警察の改革を要求する動きや、奴隷制を敷いた南部連合国に関する像など、人種差別の歴史の象徴を排除する動きも出ている。
『それでも夜は明ける(12 Years A Slave)』の脚本を担当したジョン・リドリー(John Ridley)氏は8日付のロサンゼルス・タイムズ(Los Angeles Times)の論説に寄稿し、『風と共に去りぬ』について「表現において基準を満たしていない」だけでなく、奴隷制の恐ろしさを無視し、「有色人種への最も痛ましい偏見」を永遠のものとしていると指摘し、排除されるべきだと主張した。
HBOマックスは歴史的背景に関する議論や説明を追加して配信を再開する予定だが、「差別は存在しなかった」と主張することになりかねないとの理由で編集は行わない意向を示している。
▼映画の冒頭 「古き良き南部の物語」
こんなスゴイ映画を戦前(1939年)に作っちゃうアメリカのパワー
公開されてから、すでに80年近く過ぎています
個人的感想ですが、これを超える映画は、まだ無いように思います
それにしても、その2年後に真珠湾攻撃した、日本の超無茶っぷり (T_T)
VIDEO
▼主人と黒人奴隷 の日常 「これから園遊会よ!」
園遊会にお呼ばれした主人公スカーレット(ヴィヴィアンリー)が
大好きなアシュレイに会えるかも! と期待に胸を膨らませて準備しています
この黒人奴隷のおばさん「マミー」(ハティ・マクダニエル )は
準主役と言ってよい重要な役どころ
黒人で初めて、オスカー(アカデミー助演女優賞)を受賞しました (^_^;)
VIDEO
▼スカーレットの誓い 「運命になんか、負けるもんか! 」
大富豪のお嬢が、南北戦争の敗戦と混乱で、畑の大根をかじるまで落ちぶれます
そこでこの映画最大の盛り上がり、スカーレットの魂の叫び
人間は、けして生存環境(運命)のあやつり人形ではない!
人間には自由意志があるのだ! という叫びです
長い映画(4時間)なので、この後に休憩(intermission)が入ります (^_^;)
VIDEO
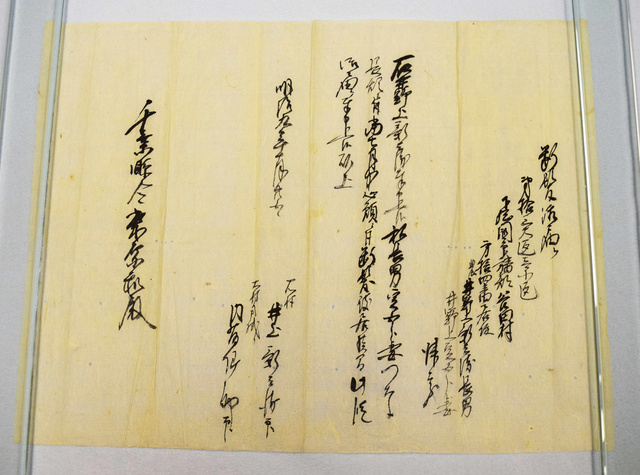













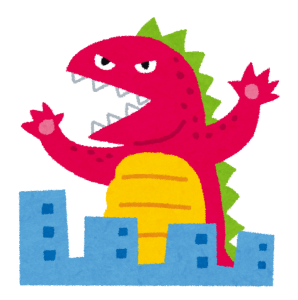
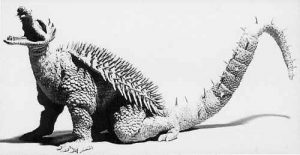




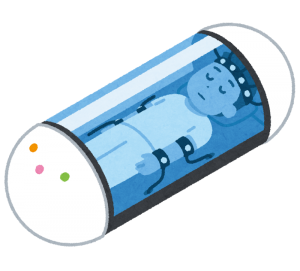



 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト