 あえてジャンルを無視して並べたリスト
あえてジャンルを無視して並べたリスト
ジャンプは600万台から ずいぶん減ったんだね
それでもスゴイけど (^_^;)
1号あたりの平均印刷部数(2012年4-6月)
01位『週刊少年ジャンプ』・2831167部(集英社)
02位『週刊少年マガジン』・1436017部(講談社)
03位『月刊少年マガジン』・736667部(講談社)
04位『コロコロコミック』・700000部(小学館)
05位『週刊文春』・698834部(文藝春秋)
06位『ビッグコミックオリジナル』・663167部(小学館)
07位『ヤングマガジン』・657625部(講談社)
08位『週刊ヤングジャンプ』・650000部(集英社)
09位『月刊ザテレビジョン』・628334部(角川グループ)
10位『ちゃお』・596667部(小学館)

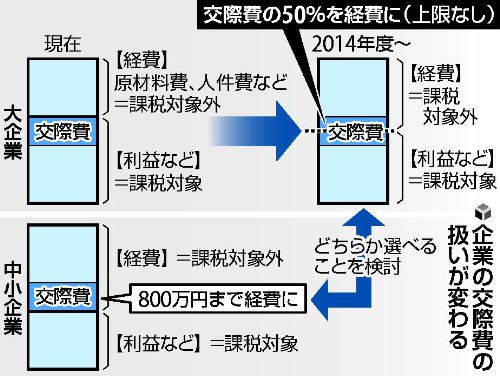
 熊谷です
熊谷です
 今年1年間に話題になった人を取り上げる年末恒例の「変わり羽子板」が5日、東京都台東区の人形専門店「久月」で披露された。
今年1年間に話題になった人を取り上げる年末恒例の「変わり羽子板」が5日、東京都台東区の人形専門店「久月」で披露された。 師走になりました。いかがお過ごしですか。
師走になりました。いかがお過ごしですか。



 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト