
幸福度は主観(感想)ですが、生活水準は客観(事実)です
健康と衣食住と人間関係(特に家族)がまあまあの水準なら、幸福になれる必要条件は満たされています
それを幸福と感じるか、不幸と感じるかは、本人の感受性(気持ちの持ちよう)の問題です
ですから、世の中の生活水準(富裕度)は非常に個人差が大きくて不公平ですが、幸福度は意外と公平なのではないかと思います
不幸なお金持ち、貧しいけれど幸福な人、たぶんいくらでもいると思います
不幸になりたければ、豊かな他人と比べるのがよいと、ブータンの事例が明らかにしています
幸福になりたければ、この逆をすればいい訳で、現在の自分よりも劣った生活条件の人を見て、現在の自分の恵まれている点を再確認(実感)するのも一つの方法です
社会全体の幸福度を上げるには、生活水準を少しずつアップさせるのが良さそうです
幸福度には、生活水準グラフの高さより傾きが重要です
高度成長期(1955~1972年)の日本人は、現在の日本人より貧しかったけど、たぶん今より幸福でした
空から爆弾が降ってこない、強制的に戦場に送られたりしない、とりあえず今日の食べ物がある、それだけで幸せな気分になれる感受性の持ち主が、いっぱいいました
さらに、昨日より今日、今日より明日が良くなるという、強い確信がありました
豊かで成熟した先進国より、貧しい発展途上国の方が、たいてい幸福度が高いのは、この辺に理由がありそうです
(^_^;)
ブータンは発展途上国ながら、2013年には北欧諸国に続いて幸福度が世界8位となり、「世界一幸せな国」として広く知られるようになった。
ブータンでは、国民が皆一様に
「雨風をしのげる家があり、
食べるものがあり、
家族がいるから幸せだ」
と答える姿が報じられたのを覚えている人もいるだろう。
しかし、ブータンは2019年度に幸福度が156か国中95位にとどまって以来、幸福度ランキングには登場していない。

「かつてブータンの幸福度が高かったのは、
情報鎖国によって他国の情報が入ってこなかったからでしょう。
情報が流入し、他国と比較できるようになったことで、
隣の芝生が青く見えるようになり、
順位が大きく下がったのです」
それまで幸せを感じていたのに、人と比べ始めたとたんに、幸福度が下がった訳だ。

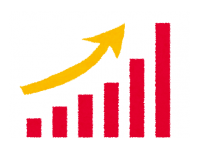

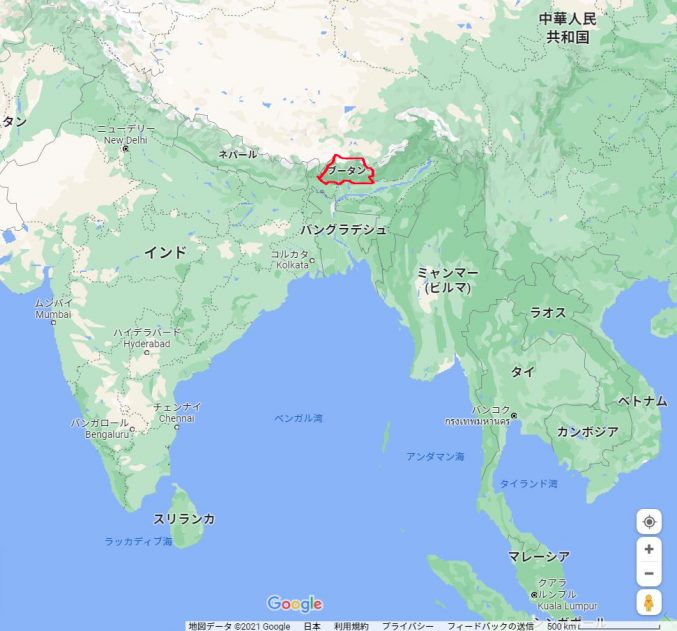
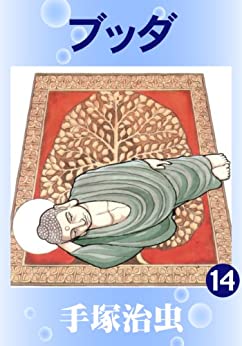





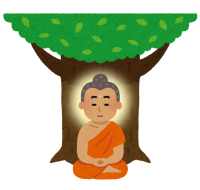
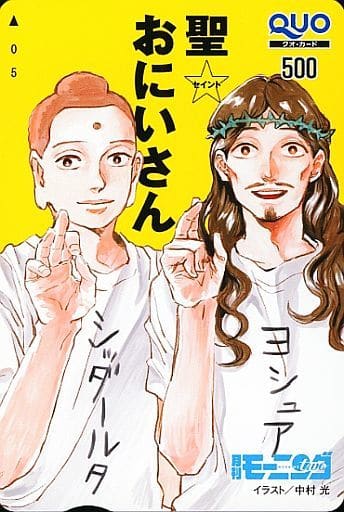
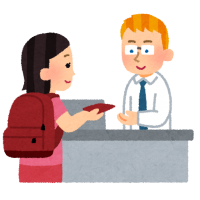







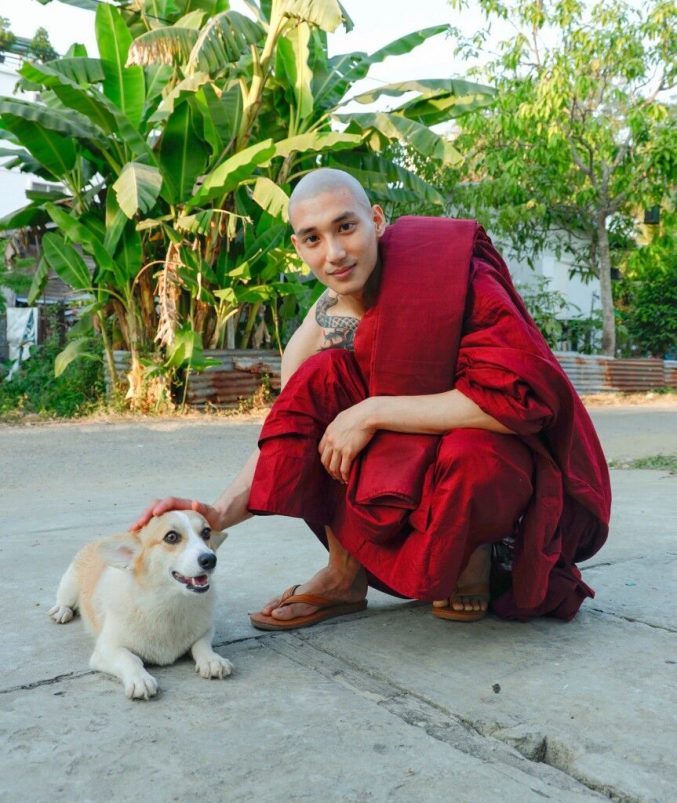

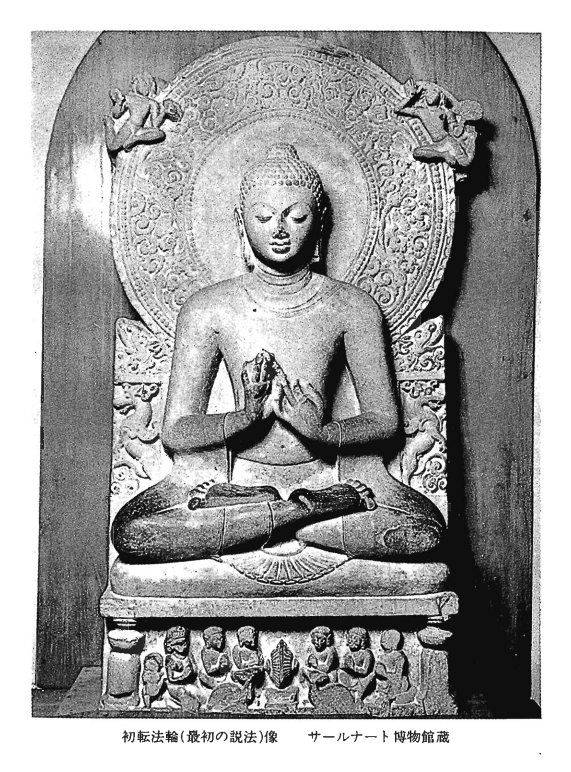
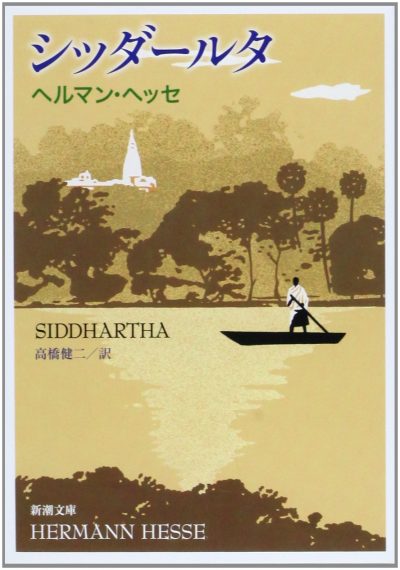
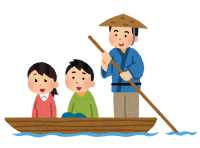




 …横須賀・軍艦クルーズ
…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス
.慶応義塾キャンパス
 ★いな吉
★いな吉 昭和音曲同好会
昭和音曲同好会
 中島ジャズ
中島ジャズ
 おにゃんこ ^ↀᴥↀ^
おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト
ラブクラフト